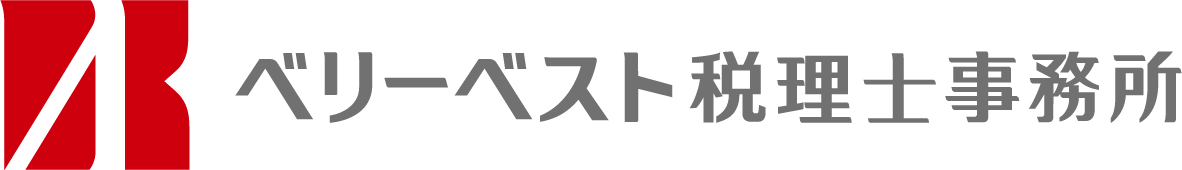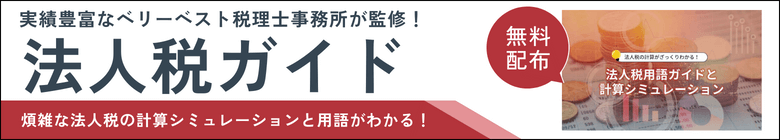創業計画書の書き方とポイントをまとめて解説【融資審査に通る!】

創業融資を受ける場合、基本的には創業計画書の提出が必要です。
しかし、初めて創業計画書を書く方は、具体的に何を書けばいいかわからないのではないでしょうか。
今回は、
- 創業計画書とはなにか
- 創業計画書の内容
- 融資審査に通るための創業計画書のポイント
について、べリーベスト税理士事務所が解説します。
創業計画書の書き方とポイントを知れば、実現可能性の高い計画書を作成できます。
実現可能性の高い計画書であれば、自ずと融資審査に通る可能性も高くなるでしょう。
ぜひ、最後までご覧ください。
税理士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
お気軽にべリーベスト税理士事務所までお問い合わせください。
1、創業計画書とは

(1)創業計画書とは
創業計画書とは、創業の動機や取り扱う商品、資金調達や事業の見通しなどの、創業をするにあたって必要な事項を記載した計画書のことです。
(2)創業計画書を書く目的
創業計画書を書く目的は、大きく分けて以下の2つです。
①創業融資の審査のため
事業を始める際、自己資金に加えて銀行などから創業融資を受ける場合があります。
創業融資を受けるための融資審査では、一般的に創業計画書の提出が必要です。
したがって、創業融資を受けようとしている場合、創業計画書を作成しなければいけません。
②創業計画を整理するため
創業計画書は、創業するにあたって必要な様々な事項が記載されるものです。
したがって、創業計画書を作成することによって、事業の内容や事業の強み・弱みなどを客観的な視点から整理することができます。
また、創業計画書があることによって、資金提供者や従業員といった関係協力者に事業のビジョンを共有できるため、円滑に協力を受けることができるようになります。
このように、創業融資のための資料だけでなく、事業の成功率を上げるという目的において必要であるといえるのです。
(3)創業計画書のテンプレート
創業計画書に決まった形はありませんが、記載する項目の参考として日本政策金融公庫の創業計画書のテンプレートがあります。
創業計画書|日本政策金融公庫
各種書式ダウンロード|国民生活事業|日本政策金融公庫
しかし、見てわかる通り記入欄が狭く、書ききれない場合があると思います。
その場合は、項目ごとに別紙にわかりやすくまとめると良いでしょう。
2、創業計画書の内容
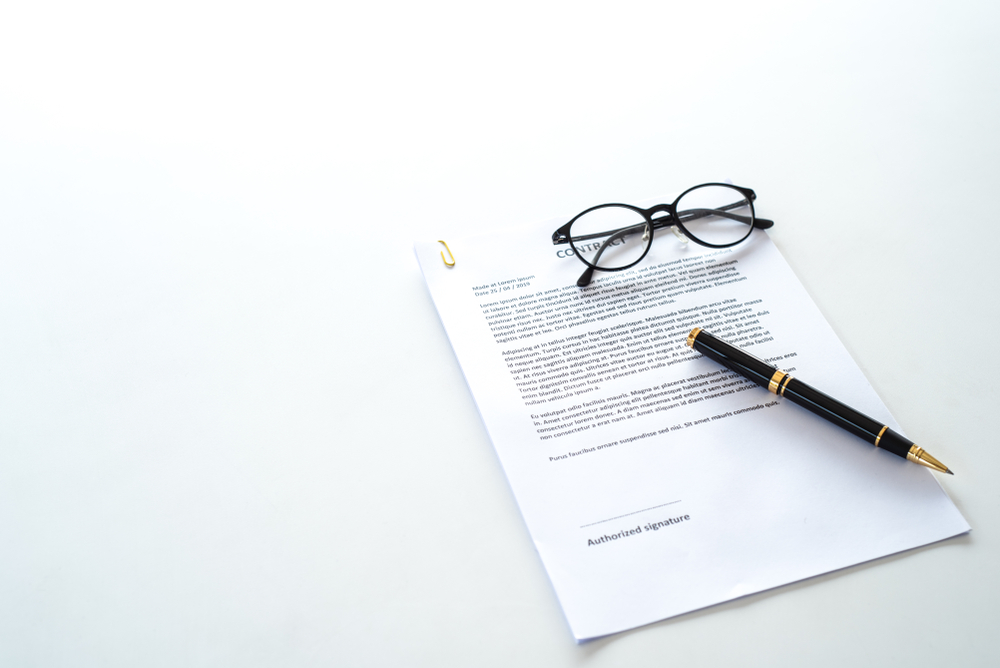
しかし、実際テンプレートを見ても、具体的にどう書けばよいのかわからないと思います。
そこで、ここでは日本政策金融公庫の創業計画書の各項目について、何をどう書けばいいのか解説していきます。
(1)創業の動機
創業の動機、目的を書く項目です。
・なぜ事業を始めるのか
・なぜその事業でなければならないのか
などについて、自身のバックグラウンドや自分の実現したい夢といった、自分と深い関連を持つ要素と絡めて書くと良いでしょう。
(2)経営者の略歴
経営者の今までの経歴、スキルを書く項目です。
・今までの職務経歴や担当業務、役職
・保有している資格や身に付けているスキル
・営業成績などの実績
などは最低限記載すべきです。
また、記載する内容が始めようとしている事業と関連するものであると、創業計画書の説得力も増すでしょう。
融資審査の際には、これらの略歴が事業にどのように活きていくのかを説明できるようにしておくと審査にプラスに働きます。
(3)取扱商品・サービス
取り扱う商品やサービスについて書く項目です。
・取扱商品・サービスの内容
・セールスポイント
・ターゲット、販売戦略
・市場・競合の分析
以上の各要素について、わかりやすくまとめられていると良いです。
各要素について具体的に書く内容は、以下の通りです。
①取扱商品・サービスの内容
どのような商品やサービスを販売するのかを記載します。
複数ある場合は、それぞれについて記載します。
②セールスポイント
セールスポイントを記載します。
セールスポイントとは、簡単に言うと商品やサービスの独自性のことです。
競合他社に簡単に真似されないような独自性や、差別化を図った点について、根拠とともにまとめられるとよいでしょう。
③ターゲット、販売戦略
ターゲットと販売戦略について記載します。
ターゲットは「誰に販売するか」、販売戦略は「どのように顧客を増やすか」ということを意味しています。
誰に販売するかが明確になると、大まかな見込み客の性質や数がわかるため、商品やサービスの売上の予測値に説得力を持たすことができます。
また、ターゲットと販売戦略、商品やサービスは、相互に論理的に納得できる関連性があると良いでしょう。
くれぐれも、商品は「美容液」、ターゲットは「小学生」、販売戦略は「新聞広告」、といった論理性のないものにならないようにご注意ください。
④市場・競合の分析
始める事業の市場や競合の分析について記載します。
競合他社の商品やサービスについて、独自性やターゲット、販売戦略について分析することで、以下のようなメリットがあります。
・本当に自社の商品やサービスは、差別化できているのかがわかる
・ターゲットがかぶっているかどうかがわかる
こうした分析結果を把握していることを記載することで、自社の商品やサービスの独自性や将来性に説得力を持たせることができます。
(4)取引先・取引関係等
販売先、仕入先などの情報を記載します。
販売先は、個人を対象としているなら「個人」、企業を対象としているなら企業名を記載します。
仕入先は、すでに決まっている場合のみ記載すれば良いです。
しかし、取引先はすでに決めてあるほうが、審査の際にはるかに好印象になります。
したがって、創業計画書を作成するまでに、取引先は明確に決めておくべきでしょう。
(5)従業員
従業員について、人数やその内訳を記載します。
(6)お借入れの状況
創業者個人の借入れ状況を記載します。
・住宅ローン
・自動車ローン
・カードローン
などが記載する借入れ状況の例としてあげられます。
創業間もないころは、創業者個人の資金力がそのまま事業の継続力に反映される場合が多いため、審査の際の重要な判断材料のひとつです。
(7)必要な資金と調達方法
どうやって資金を調達するのか、調達した資金をなにに使うのかを記載します。
記載する際は、以下の図のような形式で記載するとわかりやすいです。
|
設備購入費 機械 ¥〇〇〇 備品 ¥〇〇〇 その他 ¥〇〇〇 運転資金 仕入 ¥〇〇〇 人件費 ¥〇〇〇 家賃 ¥〇〇〇 その他 ¥〇〇〇 |
借入 甲銀行 ¥〇〇〇 乙銀行 ¥〇〇〇 |
|
出資 自分 ¥〇〇〇 佐藤さん ¥〇〇〇 鈴木さん ¥〇〇〇 |
資金使い道については、できるだけ漏れのないようにします。
創業後に想定外の出費があると、資金繰りに大きな影響を及ぼします。
また、資金の調達先については返済の必要のない自己資金の割合が多いほうが良いです。
借入の割合が多いと、定期的な利子の支払いのために資金繰りを危うくしてしまう危険性があります。
自己資金割合の目安としては、最低でも3割以上だと安心できるでしょう。
(8)事業の見通し(月平均)
創業当初と、一年後(もしくは軌道に乗った後)の事業の見通し(月平均)を記載します。
記載する際は、以下の図のような形式で記載するとわかりやすいです。
| 創業当初 | 一年後(軌道に乗った後) | ||
| 売上高 | ¥〇〇〇 | ¥〇〇〇 | |
| 売上原価 | ¥〇〇〇 | ¥〇〇〇 | |
| 経費 | 人件費 | ¥〇〇〇 | ¥〇〇〇 |
| 家賃 | ¥〇〇〇 | ¥〇〇〇 | |
| 支払利息 | ¥〇〇〇 | ¥〇〇〇 | |
| その他 | ¥〇〇〇 | ¥〇〇〇 | |
| 合計 | ¥〇〇〇 | ¥〇〇〇 | |
| 利益(=売上高ー売上原価ー経費) | ¥〇〇〇 | ¥〇〇〇 | |
売上高などの各要素の主な算定方法は、以下の通りです。
売上高
・飲食業の場合
売上高(1日あたり)= 客単価 × 席数 × 回転率
・小売業
売上高(1日あたり)= 客単価 × 1日あたりの客数
売上原価
売上原価= 売上高 × 原価率
原価率は、特別な理由がない限り、業界平均を用いると良いでしょう。
人件費
人件費(1日あたり)= 時給 × 1日当たりの労働時間 × 従業員数
家賃
借りる事務所や店舗の家賃を記載します。
支払利息
支払利息(1月あたり)= 借入金 × 利率 ×1/12
その他
その他の支出は合算して記載しますが、その内訳は別紙等にまとめておきましょう。
(9)自由記述欄
もし、政策金融公庫のテンプレートを使用する場合は、他8つの項目に当てはまらないものなどを自由に書きます。
3、融資審査に通る創業計画書のポイント

(1)創業の動機は創業の本気度を見せるとこ
融資審査の際、審査員は融資した資金をしっかり返済してくれる人かどうかを見ています。
つまり、事業が上手くいきそうかどうかと同じくらい、その人が事業をしっかり継続してくれて借金を返そうとする人なのかどうかを見ます。
したがって、創業の動機では、事業を死ぬ気で続けようとする創業者の事業に対する覚悟やモチベーションを伝えることが大切です。
(2)創業計画書は現実的かつ具体的に
創業計画書は、できる限り現実的かつ具体的に書きましょう。
あまりにも非現実的な計画では、融資審査の際に、実現可能で継続的な事業であると納得してもらうことは難しくなるでしょう。
整合性のとれた数値予測や、それを支える根拠をそろえることをおすすめします。
また、抽象的な計画も、説得性に欠けます。
各項目について詳細な内容を記載することで、計画の実現可能性が高まり、結果として融資審査に通りやすくなるはずです。
(3)補足資料を添付しても良い!
前述したように、創業計画書には決まった形式というものはありません。
しかし、創業計画書になんでもかんでも記載すればいいというわけでもありません。
あまり多くの内容を詰め込んでも、かえって計画の全体像が見えづらくなってしまいます。
その場合は、創業計画書に加えて、創業計画書に記載されている各項目を補足するような添付資料を別に作成するとよいでしょう。
たとえば、商品やサービスの項目については、写真やイラスト、市場・競合の分析に関する資料などがあると事業のイメージがより鮮明になります。
どれだけ綿密に作成された創業計画でも、伝わらなければ意味がありません。
できるだけわかりやすい創業計画書となるよう心がけることが、融資審査に通るためのコツです。
4、創業計画書の書き方に悩んだら税理士に相談しよう!

(1)創業計画書の添削を依頼してみよう!
たとえ自分では良い創業計画書を作成したつもりでも、あまりに予測が主観的であったり、説得力が欠けていたりすることは往々にしてあります。
そのため、一度他の人に創業計画書について客観的視点から意見をもらうと良いでしょう。
添削を依頼するのは、できるだけ専門的な知識や経験のある方が良いです。
例えば、税理士であれば、創業計画書について十分なアドバイスができるはずです。
(2)そもそもの創業計画についても相談!
初めて事業をする場合は、創業計画書よりも前に、そもそもの創業計画について不安がある方もいるでしょう。
その場合も、税理士に相談してみるとよいでしょう。
創業について必要な準備や知識についてのアドバイスはもちろん、創業をする際の手続きに関しても支援を受けることができます。
(3)創業した後のサポートも依頼できる!
事業を創業したらそこが終わりではなく、創業後事業を軌道に乗せ、安定的に成長させていくことが必要です。
しかし、一般的になんのトラブルもなく事業が進んでいくことは、少ないといえるでしょう。
そのため、創業後も税理士のサポートを受けることで、突発的なトラブルに見舞われた場合も安心して事業を行えます。
まとめ
以上、創業計画書について、書き方や書く際のポイントについて解説してきました。
創業計画書の質は、融資審査に通る確率や事業成功の可能性に影響します。
そのため、今回解説した内容を踏まえて、質の高い創業計画書を作成するよう心がけましょう。
作成の際は、税理士などの専門家の意見も取り入れてみることもおすすめします。
税理士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
初回のご相談は無料ですので
お気軽にべリーベスト税理士事務所までお問い合わせください。
最近の投稿

贈与税と相続税対策としての生前贈与について

ChatGPTと専門家サービス活用について

電子帳簿保存法とは?ポイントと猶予について

【中小企業向け】経営者・役員退職金の準備方法について

フリーランス(個人事業主)の最適な資産形成とは?小規模企業共済、iDeCo、つみたてNISAを徹底比較!

資産形成を成功させるポイントとは

円安が資産運用に与える影響は?円安時の投資のポイントも解説

事業再構築補助金とは?サービス産業を救う補助金の6つのポイント

マイナンバーの管理とシステム導入を企業で行うためのポイントを解説