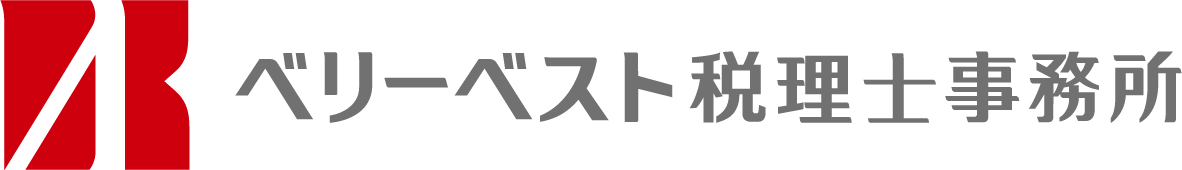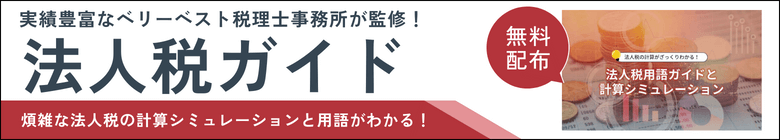消費税の中間申告・中間納付とは?経営者が知りたい5つのこと

消費税には、「中間納付」と呼ばれる確定申告以外の税金の前払制度とよばれるものが存在します。
中間納付は、すべての事業者が行う必要はなく、対象となった事業者のみ行うものです。
今回は、消費税の中間申告・中間納付の概要について説明したうえで、
- 中間申告・中間納付の対象事業者
- 中間申告・中間納付の回数や時期
- 中間申告・中間納付の計算方法
- 中間申告・中間納付の仕訳
について、解説していきます。
「消費税の中間納付がよくわからない」「初めて中間納付があることを知った」という方は、ぜひ本記事をご参考にしてください。
税理士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
お気軽にべリーベスト税理士事務所までお問い合わせください。
1、消費税の中間納付とは?

消費税の中間納付とは、年または年度の中途に申告・納税を行うことを指します。
(1)消費税の納税を複数回行うこと
消費税の申告・納税は、原則1年間に一度だけです。
しかし、ある条件を満たした事業者は中間申告の対象となり、1年間のうちに複数回の申告と納税を行うことになります。
複数回行う納付のことを、消費税の中間納付といいます。
(2)中間納付の目的
消費税の中間納付が行われる目的は、次の2つです。
- 国の税収の確保
- 納税者の負担の軽減化
原則的として、消費税の申告・納付期限は、事業年度の終了の日の翌日から2か月以内です。
個人事業主の消費税の申告・納付期限は、毎年3月末までとなります。
すべての事業者に対してこの原則を適用すると、国が税収を確保できるのは1年に一度、かつ毎年同じ時期に限定されてしまいます。
中間納付を行うことで、より確実に税収を確保できるようにしているのです。
納税者側からみると、一部、税の前払いをすることで、確定申告時期の納税額が少なくて済むというメリットがあります。
2、消費税の中間申告・中間納付の対象事業者・納付回数・納付時期

消費税の中間申告・中間納付には、前事業年度の消費税額が深く関わっています。
(1)対象となる事業者
法人の場合、前事業年度の確定消費税額(1年間の納付額)が48万円を超えると、消費税の中間納付の対象となります。
個人事業者の場合は、前年の消費税の納付額が48万円を超えた場合が対象です。
(2)納付回数と納付時期
中間納付の回数と納付時期は前事業年度または前年の消費税の納税額によって異なっています。それぞれについては下記の図をご覧ください。
| 前課税期間の 年税額 |
48万円以下 | 48万超~ 400万円以下 |
400万超~ 4,800万円以下 |
4,800万円超 |
| 中間申告の回数 | 原則 中間申告不要 |
年1回 | 年3回 | 年11回 |
| 中間納付税額 | 原則 中間申告不要 |
前課税期間の 確定消費税額の 6/12 |
前課税期間の 確定消費税額の 3/12 |
前課税期間の 確定消費税額の 1/12 |
①前事業年度または前年の確定消費税額が48万円超から400万円以下の場合
前事業年度または前年の確定消費税額が、48万円超から400万円以下の場合、中間納付の回数は年1回です。
もし、3月決算の会社だとすると、中間納付の課税期間は半年間(4~9月)となります。
納付は、その2か月後(11月末)までに行う必要があります。
②前事業年度または前年の確定消費税額が400万円超から4,800万円以下の場合
前事業年度または前年の確定消費税額が、400万円超から4,800万円以下の場合、中間納付の回数は年3回です。
もし、3月決算の会社だとすると、中間納付の課税期間と納付時期は下記の通りとなります。
| 課税期間 | 納付時期 | |
| 1回目 | 4~6月 | 8月末 |
| 2回目 | 7~9月 | 11月末 |
| 3回目 | 10~12月 | 2月末 |
③前事業年度または前年の確定消費税額が4,800万円超の場合
前事業年度または前年の確定消費税額が、4,800万円超の法人の場合、中間納付の回数は年11回です。
基本的に、課税期間となった月の2ヶ月後が納付期限となります。
ただし、最初の1ヶ月分のみ納付期限が変わりますので注意しましょう。
下記は、3月決算の法人の場合です。
| 課税期間 | 納付時期 | |
| 1回目 | 4月 | 7月末 |
| 2回目 | 5月 | 7月末 |
| 3回目 | 6月 | 8月末 |
| 4回目 | 7月 | 9月末 |
| 5回目 | 8月 | 10月末 |
| 6回目 | 9月 | 11月末 |
| 7回目 | 10月 | 12月末 |
| 8回目 | 11月 | 1月末 |
| 9回目 | 12月 | 2月末 |
| 10回目 | 1月 | 3月末 |
| 11回目 | 2月 | 4月末 |
3、消費税の中間納付額の計算方法は2つある

消費税の中間納付には、「予定申告方式」と「仮決算方式」の2つの計算方法があります。
(1)予定申告方式
「予定申告方式」とは、前事業年度または前年の確定消費税額を、中間納付の対象となる月数で割り計算する方法です。
中間納付が1回の場合、中間納付の対象になる月数は半年分です。残りの半年分は、確定申告分となります。
前事業年度または前年の確定消費税額の2分の1が、今回の中間納付で納めるべき税額となります。
予定申告方式を利用する場合、自ら納税額を計算する必要はありません。
税務署から送付されてくる納付書には、あらかじめ予定申告方式によって計算された納税額が、印字されているからです。
この金額を用いて納税を行う場合、「納税=中間申告」と見なされ、別途申告を行う必要がなくなります。
仮決算方式に比べて、手間が削減できる方式です。
(2)仮決算方式
「仮決算方式」とは、中間納付のたびに、確定申告と同じように決算処理を行い、納税額を算出する方式です。
中間納付が1回の場合、4~9月分までの数値をもとに決算を行い、納税額を算出します。
仮決算方式で納税を行う場合は、その都度中間申告を行う必要があります。
今期の数字を元に納税額を算出できるため、実態に即した金額を納税できる反面、申告の手間がかかる方式となっています。
4、消費税の中間納付の仕訳

消費税の中間納付の仕訳は、税込経理方式と税抜経理方式のどちらを適用しているかで違いがあります。
(1)税込経理方式の場合
税込経理方式の場合、中間納付と確定申告の両方の場合で、租税公課勘定を利用して仕訳します。
| 借方 | 貸方 |
| 租税公課 100,000円 | 普通預金 100,000円 |
(2)税抜経理方式の場合
税抜経理方式を適用している事業者の場合、仮払金または仮払消費税等の勘定科目を使用します。
| 借方 | 貸方 |
| 仮払消費税等 100,000円 | 普通預金 100,000円 |
確定申告の際には、仮受消費税等と仮払消費税等を相殺し、残りを未払消費税等へ計上します。
端数の関係で差額が出た時には、差額は雑収入となります。
| 借方 | 貸方 |
| 仮受消費税等 200,000円 | 仮払消費税等 100,000円
未払消費税等 100,000円 |
5、消費税の申告でお困りなら税理士へ相談を!

ここまで、消費税の中間申告・中間納付について解説してきました。
消費税の納税額が増えれば、中間申告・中間納付の回数も増え、事業者の負担も増大します。
税理士へ相談するメリットとして、以下のものが考えられます。
- 面倒な処理を減らせる
- わからないことはすぐに質問できる
- 他の税金の相談もできる
(1)面倒な処理を減らせる
消費税の処理に時間をかけられないなら、税理士に相談してみましょう。
税理士は税金のプロ。中間申告・中間納付から確定申告まで、必要な処理を適宜進めてもらえます。
自分たちで行わなければならない処理を、軽減することが可能です。
(2)わからないことはすぐに質問できる
「税務署から書類が届いたけど内容がよくわからない」
「これは支払う必要のある書類なのか?」
など、消費税や税務署の処理に関して、わからないことが出てくることもあるでしょう。
税理士と契約をしていれば、税務関連の不明点についてすぐに回答を得ることができるでしょう。
(3)他の税金の相談もできる
事業者が納めるべき税金は、消費税だけではありません。
法人税や法人事業税、源泉所得税など、会社運営には数々の税金が関わってきます。
個人事業主の場合は、所得税や住民税、個人事業税などの税金が関わります。
税理士には、税金に関するすべてを相談できるため、節税についてもアドバイスがもらえるでしょう。
まとめ
消費税の中間申告・中間納付は、前事業年度・前年の確定消費税額が48万円を超えた場合に、行う必要のある処理です。
納付回数や納付時期は、前事業年度・前年の確定消費税額によって異なっています。
中間申告・中間納付には、予定申告方式と仮決算方式があります。
申告の手間を減らしたい場合は、予定申告方式を利用しましょう。
消費税の処理が負担に感じられる事業者の方は、税理士への相談がおすすめです。
専門家による適切なアドバイスを受けることができます。
税理士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
初回のご相談は無料ですので
お気軽にべリーベスト税理士事務所までお問い合わせください。
最近の投稿

贈与税と相続税対策としての生前贈与について

ChatGPTと専門家サービス活用について

電子帳簿保存法とは?ポイントと猶予について

【中小企業向け】経営者・役員退職金の準備方法について

フリーランス(個人事業主)の最適な資産形成とは?小規模企業共済、iDeCo、つみたてNISAを徹底比較!

資産形成を成功させるポイントとは

円安が資産運用に与える影響は?円安時の投資のポイントも解説

事業再構築補助金とは?サービス産業を救う補助金の6つのポイント

マイナンバーの管理とシステム導入を企業で行うためのポイントを解説