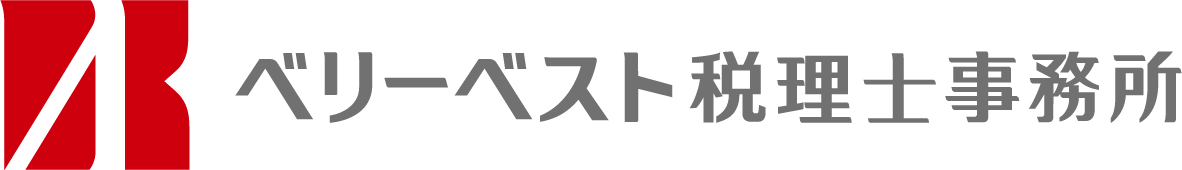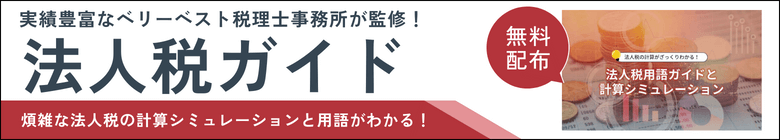【中小企業向け】経営者・役員退職金の準備方法について

中小企業にとって経営者や役員の退職金は、慰労金という側面に加えて、支払う企業側にも受け取る経営者・役員側にも、税務上の優遇措置が多いのが特徴です。
この記事では、「節税メリットを最大限に活かしつつ、将来の役員退職金を確実に準備したい」と考えている中小企業の経営者向けに、役員退職金を準備するための制度とその種類について、べリーベスト税理士事務所が分かりやすく解説していきます。
税理士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
お気軽にべリーベスト税理士事務所までお問い合わせください。
1、役員退職金とは

役員退職金の準備方法の話の前に、そもそも役員退職金とはどのようなものなのでしょうか?
まず、役員退職金には、「退職慰労金」と「死亡退職金」の2種類があります。
(1)退職慰労金
「退職慰労金」とは、取締役や監査役などの役員が退任する際に支払われるもので、勤続年数や功績などに応じて金額が計算されます。「退職慰労金」については、取締役や監査役などの役員が退職した場合に、会社はこの退職慰労金を対価として支給することができます。
一般従業員の退職金の場合は就業規則の退職金規程に基づいて支給しますが、役員退職金を支給するには定款に定めるか、株主総会の決議が必要です。この役員退職慰労金は、損金に算入することが可能で節税にもつながるものです。
(2)死亡退職金
「死亡退職金」は、遺族の生活や相続税の支払いを保証するためのものです。
死亡退職の場合、死亡日=退職日となります。支給手続きは生前退職の場合と同様で、定款の定めによるか、株主総会により支給額、支給時期、支給方法を決議します。
また、死亡退職金の損金算入時期は、株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度となります。
ただし、法人が退職金を実際に払った事業年度において損金経理をした場合は、その支払った事業年度において損金の額に算入することも認められます。
2、役員退職金の準備方法について

次に、役員退職金を準備する方法についてお話します。大きくは「預金」「有価証券」「法人保険」「小規模企業共済制度」「中小企業倒産防止共済制度」「企業型確定拠出年金」の6つの手段があります。
※「中小企業退職金共済」「特定退職金共済制度」もありますが、この2つは従業員のみが加入できる制度のため、経営者・役員は対象外となっています。
(1)預金
預金で役員退職金を準備するケースです。手間もかからず確実性は高い方法ですが、現在は金利が低いので、資金を増やすという点では非効率です。
また、特に税制上のメリットもなく、節税が可能となるものではありません。
さらに円安の局面では、円だけで資産を保有することに対するリスクがあります。
(2)有価証券
役員退職金を投資や資産運用で準備するのは、損失リスクを伴い、不確実性が高いため、あまりおすすめできません。
また、有価証券は損金算入できないのもデメリットです。
(3)法人保険
役員退職金を、法人契約の生命保険で準備する方法です。解約返戻金がある生命保険などを利用し、それを退職金に充当させることが可能になります。保険料の損金算入割合は、全額損金に算入できるタイプや、2分の1を損金算入するタイプなど、商品によって異なります。
(4)小規模企業共済制度
小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者や役員、フリーランス(個人事業主)などのための、積み立てによる退職金制度です。毎月積み立てていくタイプで、掛金は全額を所得控除できるので、高い節税効果があります。
ただし、加入後20年経たずに解約する場合には、元本割れの可能性もあります
(5)中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは、取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐために創設された共済制度です。
共済への掛金は全額損金算入が可能なので、節税対策としても効果的です。さらに無担保・無保証人での融資も可能なので、この制度を、会社の運転資金などへの備えとして活用をすることも可能です。ただし、積立上限額(解約手当金)は、最大800万円までです。
(6)確定拠出年金制度
確定拠出年金で役員退職金を準備することも可能です。
確定拠出年金とは、毎月拠出された一定の掛金とその運用収益の合計額で、将来の給付額が決定する年金制度のことです。①加入者自身が掛金を拠出する個人型確定拠出年金(iDeCo)と、②事業主が掛金を拠出する企業型確定拠出年金(企業型DC)の2種類があります。企業や加入者が拠出した掛金は加入者自ら商品を選択し資産運用するため、将来支給される年金額は、それぞれの運用結果で異なる点が特徴です。
① 個人型確定拠出年金(iDeCo)
個人型確定拠出年金(iDeCo)は、老後資金を目的とした年金制度です。加入者が掛金を拠出し、自ら金融商品を選択して運用・管理を行います。個人型確定拠出年金(iDeCo)は、掛金は最大月額68,000円まで可能で、全額所得控除が可能なため、個人として大きな節税メリットがあります。
また、すでに小規模企業共済に加入している場合でも併用は可能です。(但し、毎月の拠出額には、職業によって上限額が異なります。)
尚、個人型確定拠出年金(iDeCo)は基本的に途中解約ができず、60歳まではお金を引き出せません。積み立てた資産は一時金または年金形式で受給可能です。
② 企業型確定拠出年金(企業型DC)
企業型確定拠出年金(DC)も老後資金を目的とした年金制度ですが、個人型確定拠出年金(iDeCo)が個人で掛金を拠出し運用していく制度に対して、企業型確定拠出年金(DC)の方は、企業が掛金を拠出し、従業員(加入者)が金融商品を選択して資産運用を行います。したがって、受け取る給付金は、運用成果によって決まります。
積み立てた資産は、基本的に60歳まで解約をしない限りは引き出せません。定年退職を迎える年齢以降に、一時金(退職金)または年金形式で定められた金額を受け取る仕組みは、個人型確定拠出年金(iDeCo)と同じです。
3、中小企業の役員退職金準備に企業型確定拠出年金(企業型DC)をおすすめする理由

役員退職金を準備する方法としては、「預金」「有価証券」「法人保険」「小規模企業共済制度」「中小企業倒産防止共済制度」「企業型確定拠出年金」の6つの手段がありましたが、この中で特におすすめしたいのは、大きく税制優遇のある企業型確定拠出年金(企業型DC)です。
現状、企業型確定拠出年金導入企業のほとんどは大企業で、中小企業での導入率は1%未満と言われています。なぜ中小企業への普及がされていないのでしょうか?
その理由は、企業型確定拠出年金導入の促進をしているのは主に金融機関で、その主な収入源は加入従業員一人あたり定額の手数料です。そのため従業員数の少ない会社には積極的に案内をしてこなかったという経緯もあり、中小企業にはまだまだ広まっていない状況です。
しかし実際には、加入者1名からでも導入可能で、導入メリットも多い優れた制度となっています。
以下5つのメリットについてみていきましょう。
(1) 掛金が損金算入可能
企業型確定拠出年金(企業型DC)は、月々に拠出する掛金が非課税となります。掛金は55,000円を上限額として、経費(損金)として計上することが可能です。
(2) 運用益が非課税
企業型確定拠出年金(企業型DC)は、加入者自身が複数の金融商品の中から商品を選び、運用していくことになります。その場合の運用益は全額非課税となります。通常、NISAなどを除き、金融商品の運用益は20%ほどの所得税がかかりますので、非課税であることは大きなメリットです。
(3) 退職金受取時は税制上のメリットあり
将来、退職金として給付を受け取る時にも税制上のメリットがあります。尚、受け取りは、年金で受け取るか一時金で受け取るかが選択可能で、年金として受け取る場合は、雑所得として公的年金等控除、一時金で受け取る場合は、退職所得控除が可能です。
(4) 口座管理手数は経費計上可能
経営者・役員がiDeCoなどに加入する場合、その運用に関わる口座管理手数料などの費用はすべて個人負担ですが、企業型確定拠出年金(企業型DC)であれば、会社負担ですので、会社の経費として計上することが可能です。
(5) 従業員の福利厚生になる
経営者・役員に限らず、自社の従業員にとっても、運用益が非課税で退職金受取時の控除は大きなメリットです。
さらに、転職する際などに積立資金を転職先の会社に移管することが可能です。これらは人材獲得などの際に、会社の福利厚生としてアピールすることもできます。
4、役員退職金準備に複数制度の併用について

特に中小企業の役員退職金準備には、企業型確定拠出年金(企業型DC)をおすすめしてきましたが、既に他の制度を運用している会社や、掛金負担に不安がある会社もあると思います。そこで複数の制度を併用することも検討してみましょう。
(1) 企業型確定拠出年金(企業型DC)とiDeCoとの併用
今までは企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入している場合は、規約でiDeCoに加入できると定められている場合のみ加入できましたが、2022年10月からは、規約に定めがなくてもiDeCoに原則加入できるようになりました。経営者としては、企業型確定拠出年金(企業型DC)で会社の経費として損金算入するメリットを選ぶか、経営者本人の所得控除としてiDeCoにするか検討してみて下さい。
(2) 企業型確定拠出年金(企業型DC)と小規模企業共済と併用
小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主の積み立てによる退職金制度で、既に加入している中小企業は多いと思いますが、企業型確定拠出年金(企業型DC)との併用も可能です。
| 企業型確定拠出年金
(企業型DC) |
小規模企業共済 | |
| 貸付制度 | なし | あり |
| 運用する金融商品の選択 | 可能 | 不可 |
| 掛金(月額) | 12,000円~68,000円 | 1,000円~70,000円 |
| 中途解約 | 可能だが、条件あり | 可能 |
小規模企業共済、確定拠出年金ともに、払い込んだ掛金がその年の所得控除になるため、いずれも節税効果があります。
さらに、小規模企業共済は、経営者にとっては、事業資金を掛金の範囲内で低利率で借りることができる貸付制度があるため、入っておくといざという時に安心です。
(3) 企業型確定拠出年金(企業型DC)と中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)と併用
中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)は、取引先が倒産し、売掛金などの債権回収が困難になった場合などの備えとして加入する制度なので、こちらも既に加入している中小企業の経営者は多いと思います。企業型DC制度などの資産形成とは目的が異なる制度なので、企業型DCとの併用に特に制限はありません。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
この記事では、中小企業向けに、経営者・役員退職金制度・種類について解説してきました。
中小企業の役員退職金準備には「預金」「有価証券」「法人保険」「小規模企業共済制度」「中小企業倒産防止共済制度」「企業型確定拠出年金」といろいろありますが、特に今おすすめしたいのは、大きな税制上のメリットがあ るにもかかわらず、中小企業への導入がまだ進んでいない「企業型確定拠出年金(企業型DC)」です。既に役員退職金準備のために加入している制度に「企業型確定拠出年金(企業型DC)」を加え、併用する検討をはじめてみてはいかがでしょうか?
税理士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
初回のご相談は無料ですので
お気軽にべリーベスト税理士事務所までお問い合わせください。
最近の投稿

贈与税と相続税対策としての生前贈与について

ChatGPTと専門家サービス活用について

電子帳簿保存法とは?ポイントと猶予について

【中小企業向け】経営者・役員退職金の準備方法について

フリーランス(個人事業主)の最適な資産形成とは?小規模企業共済、iDeCo、つみたてNISAを徹底比較!

資産形成を成功させるポイントとは

円安が資産運用に与える影響は?円安時の投資のポイントも解説

事業再構築補助金とは?サービス産業を救う補助金の6つのポイント

マイナンバーの管理とシステム導入を企業で行うためのポイントを解説