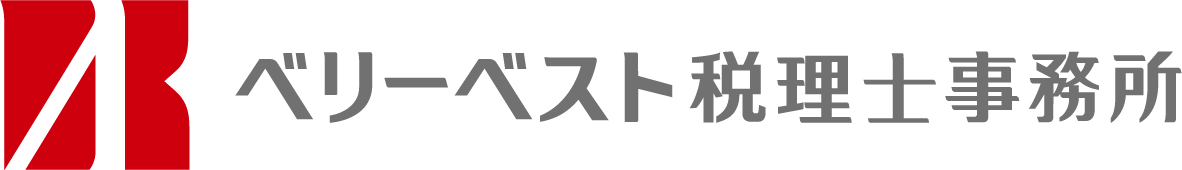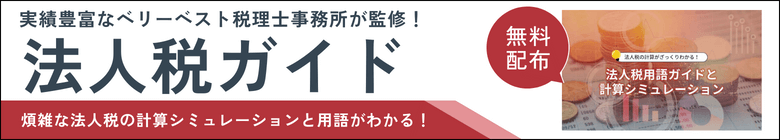資本金1000万以下で起業可能?起業で知りたい資本金のこと5つ

資本金1000万円超での起業と、1000万円以下での起業には、どのような違いがあるのだろう……。
起業を検討されている方のなかには、資本金の額でお悩みの方も少なくないのではないでしょうか。
一般的に、起業前の段階では資本金を1000万円超えにするのか、1000万円以下にするかで悩まれる方が多くいらっしゃいます。
資本金が1000万円を超えているかどうかで、消費税額や法人住民税額などが変わってくるためです。
消費税については、資本金が1000万円以上で納税義務者となります。
法人住民税については、資本金が1000万円超で均等割の額が変わります。
今回は、資本金とはどういうものかについて説明したうえで、
- 資本金を1000万円未満にするメリット
- 資本金を1000万円未満にするデメリット
- 資本金が1000万円を超えると下請法の対象になる
について解説していきます。
「資本金をいくらにすべきか迷っている」
「資本金は1000万円なくてはだめなの?」
などとお悩みの方は、ぜひ本記事をご参考にください。
税理士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
お気軽にべリーベスト税理士事務所までお問い合わせください。
1、そもそも資本金とは?

そもそも資本金とは何なのか、本章では資本金の基本について解説していきます。
(1)資本金の概要
資本金とは、会社設立までに、株主や投資家から受けた「出資金」のことです。
会社を設立するには、設備を整えるなどで、資金が必要になります。
これらに充てるため、株主や投資家から調達した資金を資本金といいます。
(2)資本金からわかること
資本金の額からわかることは、「会社の規模」と「会社の体力」です。
資本金の額が多ければ多いほど、規模の大きな会社であることが想定されます。
「多くの資金を集められる」というような信用力があると判断できるため、資本金が多ければ、いざというときに体力のある会社といえるでしょう。
(3)資本金が多いと何が良いのか
前述のとおり、資本金は株主や投資家から集めたお金です。
多額の資本金が集められるということは、それだけ、株主や投資家から信用をされている会社であるとわかります。
経営の面においても、信頼のおける会社であると判断されることが多いでしょう。
2、資本金を1000万円未満にするメリット
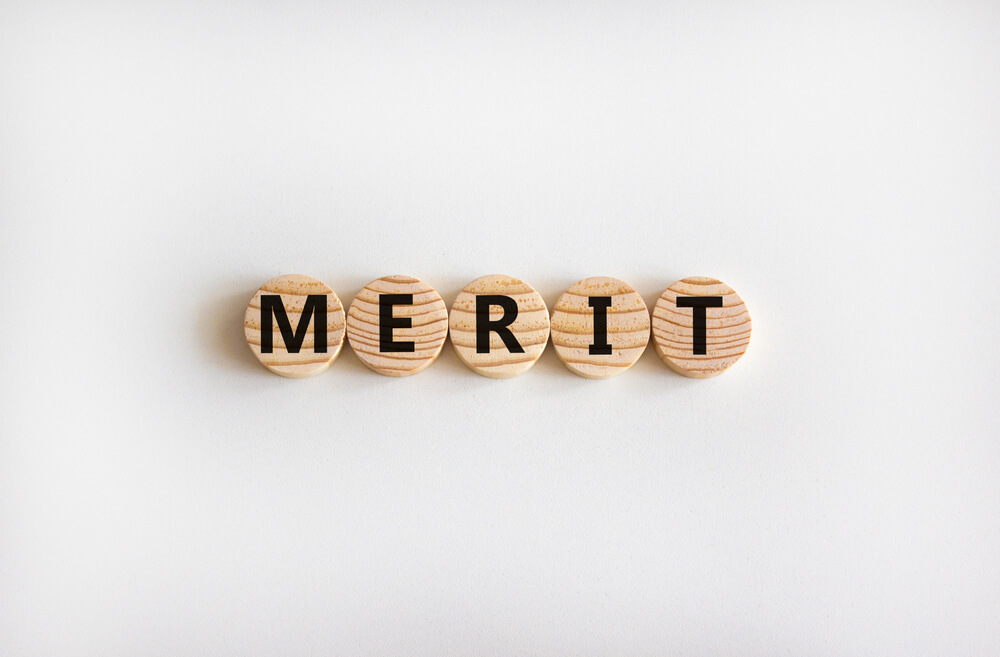
本章では、資本金を1000万円未満にすることによって、得られるメリットを紹介します。
「資本金が少ない=倒産しやすい会社」ではありません。その理由についても、解説していきます。
(1)消費税が最長2年間免除
課税期間に係る課税売上高が1000万円を超える事業者は課税事業者となり、消費税を納税する義務が発生します。
しかし、新たに設立された法人で、かつ資本金の額が1000万円未満の事業者に対しては、最長2年間、消費税の納税が免税されるのです。
新たに設立された法人については、設立1期目及び2期目の基準期間はありませんので、原則として、納税義務が免除されます。
しかし、基準期間のない事業年度であっても、以下の場合であれば、納税義務は免除されません。
- 事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1000万円以上の場合
- 特定新規設立法人に該当する場合
(引用:No.6501 納税義務の免除|国税庁)
資本金が1000万円以上の場合、設立年度から、課税事業者となってしまいます。
(2)法人住民税が少なくて済む
法人住民税には、「所得割」と「均等割」があり、均等割の計算には、資本金の額が関わってきます。
簡単にいうと、資本金額が1000万円以下の事業者の方が、納税額が少なくて済むのです。
例えば、東京都の場合、資本金額が1000万円以下かつ従業員数が50人以下の会社の均等割額は、7万円です。
一方、資本金額が1000万円超~1億円以下かつ従業員数が50人以下になると、均等割額は、18万円となります。
資本金が1000万円以下の会社の方が、11万円安くなる計算です。
法人住民税の均等割額は、自治体によって異なりますので、詳細な金額は各自治体の情報を参考にしてください。
(3)資本金1000万円以下の会社は倒産しやすいわけではない
本章の冒頭でも説明したとおり、資本金の額と会社がすぐに倒産するかどうかは、直結していません。
資本金は、増資をしない限り、会社を設立した当時の会社規模を表しています。
その後どんなに売上が伸びても、従業員が増えて会社の規模が拡大したとしても、資本金の額には反映されません。
資本金の額が少ない会社は、すぐに倒産してしまうと一概には言えないのです。
倒産の可能性が高いかどうかは、会社全体の数値をみて判断する必要があります。
3、資本金を1000万円未満にするデメリット

以前は、資本金が1000万円以上でなければ、株式会社を設立することができませんでした。
その名残で、「資本金が1000万円未満の会社」に対して、不安を抱く方もいるでしょう。
資本金1000万円未満で起業する場合は、「世間から不安視される可能性がある」ことを考慮しておきましょう。
特に、融資を受ける際には、資本金が少なすぎると不利になるケースがあります。
例えば、日本政策金融公庫から融資を受ける場合、資本金は融資金額の最低10分の1が必要です。
現在、資本金は1円から株式会社の設立が可能です。
しかし、だからといってあまりに低い金額に設定をしてしまうと、融資を受けられない事態を引き起こすことになりかねません。
起業をする際には、将来のことも検討したうえで、資本金額を決定するようにしましょう。
4、資本金が1000万円を超えると下請法の対象に

資本金が、1000万円を超えると下請法の対象となり、下請け企業に対してさまざまな義務を負うことになります。
本章では、下請法の概要と下請け企業に対する義務について解説します。
(1)下請法とは下請け企業を保護する法律
下請法とは、下請け企業を保護するための法律です。正式名称を「下請代金支払遅延等防止法」といいます。
力の強い親事業者からの不正の強要や、支払の未払から下請け企業を守るために、制定されました。
(2)資本金1000万円を超えると義務が生じる
下請法では、資本金が1000万円を超えると親事業者に該当します。
親事業者になると、下請け企業に対して下記の義務を果たす必要が生じるのです。
- 書面の交付義務
- 支払期日を定める義務
- 書類の作成・保存義務
- 遅延利息の支払義務
資本金を検討する際は、資本金額が1000万円を超えると、下請法の親事業者に該当することを覚えておきましょう。
違反したときには、罰金や勧告を受ける可能性があるので、注意が必要です。
5、資本金の額でお悩みなら税理士へ相談を!

「資本金がいくらあれば十分なのかわからない」
「資本金の額を変更したら何か影響が出るのか知りたい」
上記のようなお悩みを持っている方は、税理士への相談をおすすめします。
本章では、税理士へ相談するメリットを紹介します。
- 会社にあわせた適切なアドバイスがもらえる
- 会社設立に関するその他の事項も合わせて相談できる
- 会社設立後も相談できる
(1)会社にあわせた適切なアドバイスがもらえる
ここまで説明してきたとおり、資本金の額は、税金や会社の信用に影響を与えます。
「1人では決められない」「自社にとってベストな資本金額を知りたい」という状況もあるでしょう。
以上のような状況の方は、ぜひ一度税理士へご相談ください。
会社の状況に合わせた適切なアドバイスが得られるでしょう。
(2)会社設立に関するその他の事項も合わせて相談できる
起業する際には、資本金以外にも検討すべきことがたくさんあります。
資本金以外の税金や手続きについても、税理士に相談をすることが可能です。
税理士は、さまざまな会社の設立に関わってきています。
そのため、今までの多くの経験を活かしたアドバイスが得られるでしょう。
税理士は、経営者の心強い相談者となってくれます。
(3)会社設立後も相談できる
会社は、設立してからがスタート。運営していくと、さまざまな問題が出てきます。
運営上でさまざまな問題が発生した場合でも、会社設立前から取引のある税理士であれば、会社の説明や引継ぎを行う必要がありません。
税理士へ、スムーズに問題の対応を依頼できるでしょう。
まとめ
資本金が1000万円未満の場合は消費税の負担を、1000万円以下の場合は法人住民税の負担を、抑えることが可能です。
しかし、資本金が1000万円に満たない会社を不安視する声もあります。
資本金が少なすぎると、融資など借入ができなくなる可能性もあります。
資本金の額を決めるときには、メリット・デメリットをどちらも理解したうえで、資本金の額を検討しましょう。
下請法についても、考慮をする必要があります。
資本金の検討に際し、疑問点や不安がある方は、税理士へ一度ご相談をください。
数々の会社の設立に携わってきた経験を活かし、会社の事情に合った適切なアドバイスを受けることができます。
税理士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
初回のご相談は無料ですので
お気軽にべリーベスト税理士事務所までお問い合わせください。
最近の投稿

贈与税と相続税対策としての生前贈与について

ChatGPTと専門家サービス活用について

電子帳簿保存法とは?ポイントと猶予について

【中小企業向け】経営者・役員退職金の準備方法について

フリーランス(個人事業主)の最適な資産形成とは?小規模企業共済、iDeCo、つみたてNISAを徹底比較!

資産形成を成功させるポイントとは

円安が資産運用に与える影響は?円安時の投資のポイントも解説

事業再構築補助金とは?サービス産業を救う補助金の6つのポイント

マイナンバーの管理とシステム導入を企業で行うためのポイントを解説