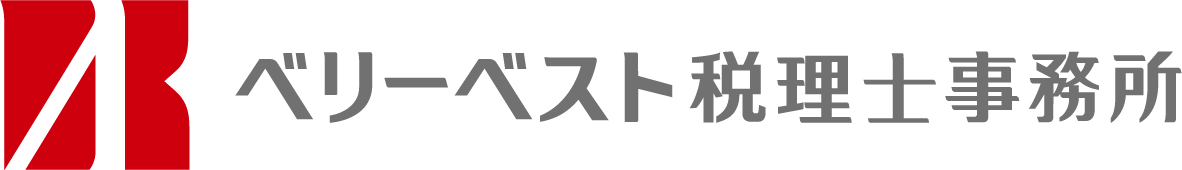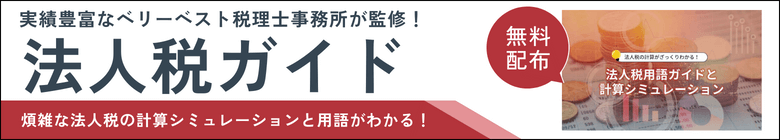経営者保証に関するガイドラインで個人保証を外すコツを徹底解説!
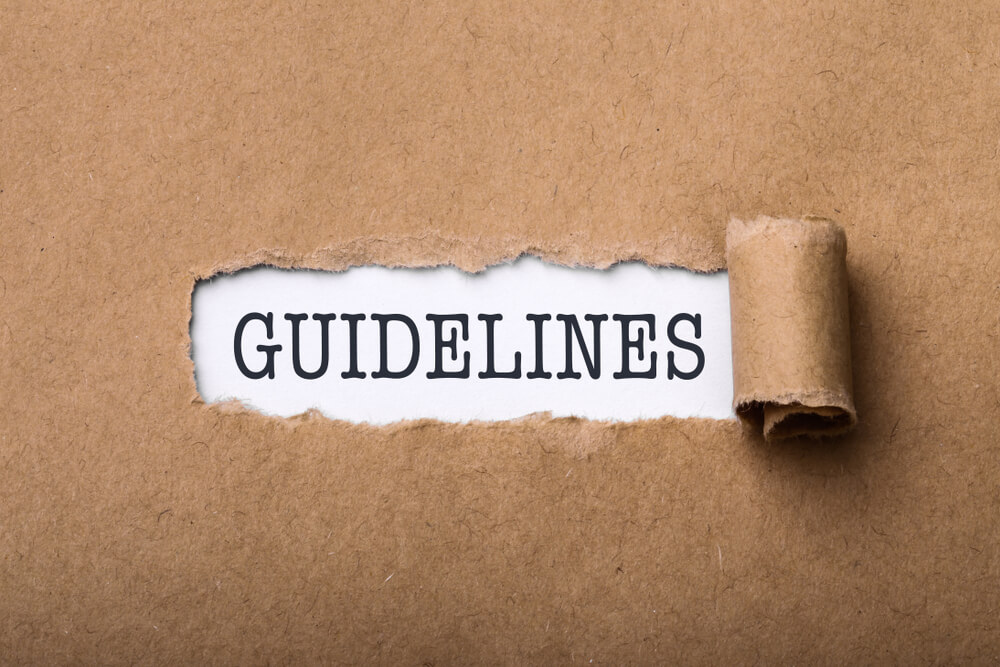
経営者保証に関するガイドラインをご存知でしょうか?
「会社の資金繰りが苦しいので融資を受けたいが、個人保証はしたくない」というのは、中小企業の経営者の大きな悩みの1つかもしれません。
個人保証をすると個人として弁済の責任を負わなければならないので、融資を受けることを躊躇するのも無理はないでしょう。
そこで検討したいのが、「経営者保証に関するガイドライン」です。
経営者保証に関するガイドラインに従うと、個人保証なしで融資を受けたり、すでに設定されている個人保証を外してもらったりなどを期待できます。
今回は、経営者保証ガイドラインの概要について説明したうえで、
- 経営者保証に関するガイドラインの活用方法
- 経営者保証に関するガイドラインで個人保証を外すポイント
などについて、解説します。
経営者保証に関するガイドラインについて知りたいと思っている方や、個人保証に頼りすぎない柔軟な融資を受けたいと考えている方のご参考になれば幸いです。
税理士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
お気軽にべリーベスト税理士事務所までお問い合わせください。
1、経営者保証に関するガイドラインとは?

本章では、個人保証を外しやすくなるなどのメリットが期待できる、経営者保証ガイドラインについて解説します。
(1)経営者保証に関するガイドラインの概要
「経営者保証ガイドライン」とは、金融機関が中小企業に融資を行なう場合に、個人保証に頼りすぎることなく、適切な保証契約をするためのガイドラインです。
従来の個人保証は、中小企業が融資を受けるための手段になる反面、経営者が個人として責任を負うことになるというデメリットがありました。
以上のことから、思い切った事業展開や、戦略的な事業の撤退などをしにくくなるという問題点もありました。
そこで、信用力の低い中小企業が、柔軟に資金調達できるような環境の形成が求められます。
経営者保証ガイドラインに基づいて融資の交渉や手続きをすることで、個人保証に頼りすぎない柔軟な融資の実現が可能です。
経営者保証ガイドラインには、法的な拘束力はありません。
しかし、当事者がガイドラインを尊重することが要請されているので、ガイドラインに従えば、適切な保証契約をすることが期待できます。
(2)経営者保証に関するガイドラインの効果
経営者保証に関するガイドラインに従って手続きをした場合、一般に以下のような効果が期待できます。
- 個人保証なしで融資を受けられる
- 個人保証を外すことができる
- 一定の資産を手元に残しながら債務整理ができる
- 経営者が信用情報機関への登録を行わない
ただし、ガイドラインはあくまで任意なので、実際にどのような効果が得られるか、最終的には金融機関の判断によります。
(3)経営者保証に関するガイドラインの要件
経営者保証に関するガイドラインは、以下の全ての要件を満たす保証契約に関して適用されます。
- 保証契約の主たる債務者が中小企業である
- 保証人が個人であり、かつ主たる債務者の経営者である(例外あり)
- 主たる債務者と保証人の双方が弁済について誠実である
- 債権者の請求に応じて、財産・負債の状況などについて適時適切に開示している
- 主たる債務者と保証人が反社会的勢力ではない
要件のポイントを簡潔にまとめると、以下のとおりです。
- 中小企業の経営者が、自分の会社の債務について個人保証をしている
- 弁済に誠実であり、かつ財産状況について適切に開示している
2、経営者保証に関するガイドラインの活用方法

経営者保証に関するガイドラインの活用方法として、以下の2点について解説します。
- 個人保証なしで融資を受けやすくなる
- 個人保証を外して事業承継しやすくなる
(1)個人保証なしで融資を受けやすくする
経営者保証ガイドラインに従って金融機関と融資の交渉をすると、個人保証なしで融資を受けやすくなります。
会社の経営者が個人保証をした場合、もし会社の業績が悪化して弁済ができなくなれば、経営者が個人として保証した債務を弁済しなければなりません。
会社の債務を返済するために、経営者が自分の預貯金や不動産などを弁済にあてた場合、経営者や家族の生活に影響が生じます。
ガイドラインに従った結果、個人保証なしで融資を受けることができれば、上記のようなリスクを回避できます。
(2)個人保証を外して事業承継をしやすくする
事業承継とは、会社の経営を後継者に引き継ぐことです。
後継者不足に悩む中小企業が少なくないので、事業承継をスムーズに行えるかどうかは、多くの企業にとって重要な課題です。
会社の経営者が個人保証をしている場合、後継者が会社を引き継ぐ際に、新たに個人保証を引き受けなければならない可能性があります。
ガイドラインに従うことで、もし個人保証を外すことができれば、個人保証の引き受けというリスクを背負わずに、事業承継をスムーズに行える可能性があります。
3、経営者保証に関するガイドラインで個人保証を外すには

会社の経営において個人保証をすると、事業から撤退しにくくなるなどのデメリットがあるので、個人保証を外すことを検討するのは有意義です。
経営者保証に関するガイドラインを活用して個人保証を外すには、3つのポイントを押さえることが大切です。
本章では、個人保証をするデメリットと、個人保証を外すポイント3つを解説します。
(1)個人保証をするデメリット
会社の経営のために個人保証をすると、次のようなデメリットがあります。
- 個人の生活・財産に影響する可能性がある
- 事業から撤退しにくくなる
- 事業承継をしにくくなる
①個人の生活・財産に影響する可能性がある
個人事業主とは異なり、法人としての会社の債務は、原則として経営者個人の債務にはなりません。
しかし、経営者が会社のために個人保証をすると、会社の経営がうまくいかなくなった場合に、最終的に経営者が個人として債務の弁済をしなければならない可能性があります。
個人として所有する預貯金や不動産など、経営者自身の財産を切り崩して弁済にあてなければならないなど、個人の生活・財産に影響する可能性があります。
②事業から撤退しにくくなる
会社が株式会社などの場合、経営者は有限責任なので、会社の経営が悪化しても経営者自身は原則として債務を負担しません。
必要であれば会社をたたんで、事業から撤退することを検討できます。
しかし、会社の債務について経営者が個人保証をしている場合、会社の経営が悪化すれば、経営者が債務を負担しなければなりません。
個人保証をしていると、会社の経営状態が経営者に直接影響するので、事業から撤退しにくくなります。
会社の経営を改善するために、採算性の悪い事業を続けなければならないという点が、デメリットです。
③事業承継をしにくくなる
経営者が会社の債務について個人保証をしている場合、事業承継をするにあたって、後継者が個人保証を新たに引き受けるのが一般的です。
会社を引き継ぐこと自体が重い責任であるところ、加えて個人として会社の債務を保証しなければならないとなると、責任はさらに増大します。
結果として、個人保証を引き受けることを嫌がって後継者がなかなか見つからず、事業承継をスムーズに行なうのが難しくなるというデメリットが生じます。
(2)経営者保証に関するガイドラインで個人保証を外すポイント
経営者保証に関するガイドラインに従って、債権者(金融機関)に個人保証を外してもらいやすくするには、3つのポイントを押さえる必要があります。
①法人と個人の一体性を解消する
中小企業などでは、法人としての会社と経営者としての個人の境界があいまいで、一体性が解消されていない場合があります。
たとえば、会社の経費で経営者に多額の貸付金を出してしまうなどです。
法人と個人の一体性を解消し、適切な事業活動を心がけることで、経営者保証を外してもらいやすくなります。
法人と個人の一体性を解消する主なポイントは、以下のとおりです。
- 個人が工場や営業車などの資産を所有している場合は「法人所有」にする
- 必要性が認められない経営者への貸付は行わない
- 個人としての飲食代は経費にしない
- 自宅が店舗を兼ねているなど分離が困難な場合は適切な賃料を支払う
②財務基盤を強化する
経営者保証は、主たる債務者の信用力を補完する手段の1つとして、機能している側面があります。
経営者保証を外しやすくするためのポイントは、次のとおりです。
- 会社の財務基盤を強化して返済能力を向上させる
- 経営者保証とは別の側面から信用力を上げる
財務基盤の強化を心がけた結果、財務状況や経営成績が改善することで、他の手段によって資金調達をしやすくなるメリットもあります。
一般的に、財務基盤が強化されたと判断されやすいのは、以下のような場合です。
- 業績が好調で十分なキャッシュフローがあり、内部留保も潤沢である
- 業績はやや不安定なものの、内部留保が潤沢なので、債務の全額の返済が可能と判断できる
- 内部留保は潤沢ではないものの、好業績が続いているので、今後も借入を順調に返済できる見込みがある
③財務状況について適切な情報開示をする
会社の財務状況が不透明な場合、金融機関はリスクを感じて、経営者保証などの担保を求める傾向にあります。
財務状況について適切な情報開示をすると、金融機関の信頼感が増して、経営者保証を外してもらうことに繋がります。
情報開示すべき主な項目は、以下のとおりです。
- 資産と負債の状況(会社と経営者について)
- 事業計画
- 業績の見通し
情報開示する場合には、以下のポイントを押さえることも重要です。
- 信頼性の高い情報を採用し、親切かつ丁寧に説明する
- 税理士などの専門家の検証を受けることで、情報の質を向上させる
- 開示後に事業計画や見通しなどに変動が生じた場合は、適宜報告する
(3)個人保証以外の融資方法
個人保証以外の融資方法として、次のようなものがあります。
- 停止(解除)条件付きの保証契約
- ABL
- 金利の一定の上乗せ など
個人保証を外すかわりの融資方法として、金融機関に提案される可能性があるので、それぞれ解説します。
①停止条件または解除条件付きの保証契約
「停止条件付きの保証契約」とは、主たる債務者(会社)が特約条項に抵触しない限り、保証債務の効力が発生しない保証契約のことです。
要約すると、「会社が特約条項を破らない限り保証責任を負わなくてよい」という意味です。
たとえば、「社内の管理体制を定期的に報告している限り、保証責任を負わない」などが考えられます。
「解除条件付きの保証契約」とは、主たる債務者が特約条項を充足する場合は、保証債務の効力が失われる保証契約のことです。
要約すると、「会社が特約条項を満たした場合は保証責任から解放される」という意味になります。
たとえば、「一定期間の間に決められた内容を会社がきちんと行えば、保証契約が解除されて責任を免れる」などです。
経営者保証に関して、停止条件または解除条件付きの保証契約に利用される主な特約条項(特則)は、以下のとおりです。
- 役員や株主の変更などがあった場合に、債権者に報告しなければならない
- 試算表などの財務状況に関する書類について、債権者に提出しなければならない
- 担保の提供などを行う場合、債権者の承諾を得なければならない
- 外部機関を含めての監査体制を確立するなど、社内の管理体制について報告しなければならない
②ABL
ABL(Asset Based Lending)とは、企業が保有する在庫や売掛金などを担保にして、融資を行なう手法のことです。流動資産担保融資と呼ばれることもあります。
ABLによって融資される金額は、在庫や売掛金などの担保評価額に連動して決まるのが一般的です。
不動産を担保にする場合、企業の業績とは関係なく、基本的に不動産の評価額によって融資される金額が決まります。
一方、ABLによって在庫や売掛金を担保にする場合、評価額は企業の業績によって左右されやすいのが特徴です。
一般的に、担保になることが多いのは不動産ですが、在庫や売掛金などを担保として活用することで、従来よりも円滑な資金調達が可能になるのがABLのメリットです。
ABLによって融資をする場合、債権者は企業の在庫や売掛金などを継続的にモニタリングし、担保としてきちんと機能するかを確認する必要があります。
定期的なモニタリングによって、企業の経営状態をより把握しやすくなるので、信用リスク管理の強化が期待できるのが、債権者にとってのメリットです。
③金利の一定の上乗せ
経営者保証を求めないかわりに、金利の一定の上乗せをして、信用リスクの増大に備える方法もあります。
上乗せされる金利がどのくらいになるかは、一般に以下の基準によって決められます。
- 企業の社内管理体制の整備状況
- 経営改善の見通し
- 企業の規模・事業内容・収益力 など
債務者にとっては、個人保証をしなくて済むのがメリットですが、金利の上乗せがされる分、返済の負担が重くなるのがデメリットです。
「個人保証をする場合」と「金利を上乗せする場合」を比較して、どの程度金利の負担が重くなるかを債務者に提示することで、債務者に選択肢を提案する方法もあります。
最終的に、債務者が個人保証を選択したとしても、債権者は保証契約の必要性などについて丁寧かつ具体的に説明し、適切な金額を設定するよう努めることが要求されます。
まとめ
経営者保証ガイドラインは、個人保証に頼りすぎない健全な融資を実現するために策定されたガイドラインです。
ガイドラインに従うことで、個人保証なしで融資を受けたり、すでに設定された個人保証を外して事業承継に備えるなどの効果が期待できます。
経営者保証ガイドラインに従うには、財務基盤を強化したり、財務状況について適切な情報開示を行なったりするなどの工夫が重要です。
財務状況でお困りの場合には、税理士に依頼することで、、
- 財務基盤の強化や財務状況に開示などについて適切な指導を得られる
- 各種の資金調達についてのアドバイスを受けられる
などのメリットがあるため、おすすめです。
経営者保証に関するガイドラインを含め資金調達などで不安や悩みがある場合には、一度税理士へ相談しましょう。
税理士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
初回のご相談は無料ですので
お気軽にべリーベスト税理士事務所までお問い合わせください。
最近の投稿

贈与税と相続税対策としての生前贈与について

ChatGPTと専門家サービス活用について

電子帳簿保存法とは?ポイントと猶予について

【中小企業向け】経営者・役員退職金の準備方法について

フリーランス(個人事業主)の最適な資産形成とは?小規模企業共済、iDeCo、つみたてNISAを徹底比較!

資産形成を成功させるポイントとは

円安が資産運用に与える影響は?円安時の投資のポイントも解説

事業再構築補助金とは?サービス産業を救う補助金の6つのポイント

マイナンバーの管理とシステム導入を企業で行うためのポイントを解説