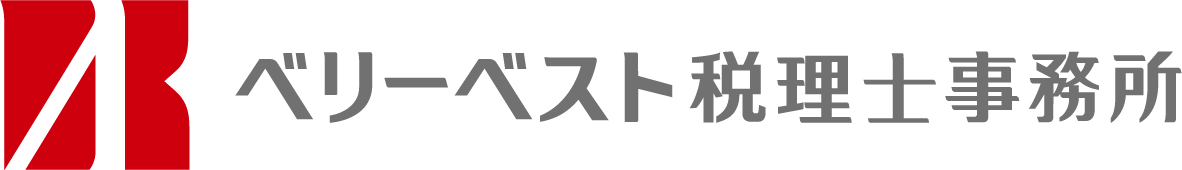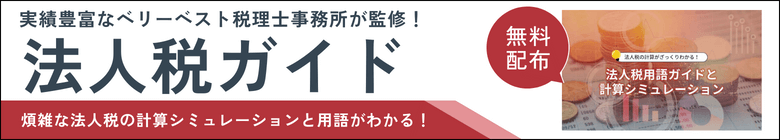ストックオプションとは?|SO導入を決める前に知るべき4つのこと

ストックオプションとは一体どんな制度なの?
ストックオプションを導入すると良いところあるの?
「ストックオプション」という言葉は、会社で働いている方なら、一度は聞いたことがあるかもしれません。
株式上場を前にして、ストックオプションを導入するか悩んでいる経営者の方もいるのではないでしょうか。
ストックオプションは、効果的な「インセンティブ制度」として注目が高まっています。
ストックオプションを導入することによって、どういったメリットやデメリットがあるのか気になりますよね。
本記事では、ストックオプションの概要からメリットやデメリットまで解説します。
具体的に、
- ストックオプションとは?
- ストックオプションのメリット・デメリット
- ストックオプション導入のポイント
などについて解説します。
本記事が、ストックオプションの導入を決める参考になれば幸いです。
税理士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
お気軽にべリーベスト税理士事務所までお問い合わせください。
1、ストックオプションとは?|ストックオプションの概要

本章では、
- ストックオプションの概要
- ストックオプションの仕組み
- ストックオプションの種類
について解説します。
(1)ストックオプションとは?
ストックオプションとは、「新株予約権」の1つであり、会社が発行する株式をあらかじめ一定の価格で取得できる権利のことをいいます。
「新株予約権」の中に、「ストックオプション」という言葉が含まれていることになります。
「ストックオプション」の特徴は、株式をあらかじめ一定の価格で取得できる権利の対象が、経営者や従業員などの社内の人間に限られている点です。
簡単に説明すると、ストックオプションは、「自社の株式を安く購入することができる権利」であり、「従業員のインセンティブを高める制度」です。
一定の価格のことを「権利行使価格」と呼び、市場よりも優遇された価格で自社株式を購入することができます。
権利行使価格で購入した株式は、会社の株価が上昇した際に売却すると、権利行使価格と株価の差額分の「キャピタルゲイン」を得ることができます。
(2)ストックオプションの仕組み
ストックオプションについての仕組みを解説するために、簡単な事例を紹介します。
例えば、現在の株価が1000円の時に、「今後5年間は自社株を500円の権利行使価格で購入できる」というストックオプションを付与されたとします。
この時点で自社株を5万円で100株式を購入し、年数が経つにつれ株価が徐々に上昇し1500円になったとします。
株価が1500円になった時点で、所有している株式を全て売却すれば、1株1000円のキャピタルゲインを得ることができます。
5万円で購入した株式で、10万円のキャピタルゲインを獲得することが可能となるのです。
また、5年後に株価が3000円となった場合にも、市場価格よりも大幅に安い権利行使価格の500円で購入することができます。
(3)ストックオプションの種類
ストックオプションには前章で紹介したような通常のストックオプションに加えて、他に5つの種類があります。
5つの種類とは、次のとおりです。
- 無償税制適格ストックオプション
- 無償税制非適格オプション
- 信託型ストックオプション
- 有償型ストックオプション
- 株式報酬型ストックオプション
①無償税制適格ストックオプション
もっとも一般的なストックオプションは、無償税制適格ストックオプションを指していることが多いです。
「無償税制適格ストックオプション」は、無償で発行された新株予約権に対して、税制適格条件を満たしてるストックオプションのことです。
税制適格の条件を満たすことによって、株式を保有するタイミングではなく、株式売却時のタイミングで課税される優遇措置の適用を受けることができます。
税制適格の条件は、以下の4点に関わってきます。
- 発行形態
- 付与対象者
- 権利行使価格
- 権利行使期間
以上の4点全てにおいて規定されている条件を満たせば、優遇措置が受けられることになるのです。
具体的には、譲渡所得として20.315%の税率で所得税が課税されます。
②無償税制非適格ストックオプション
「無償税制非適格ストックオプション」は、税制適格要件を満たしていない無償の新株予約権のことをいいます。
税制適格を満たしていない場合、株式を保有する時と株式売却時の両方のタイミングで、課税されるストックオプションです。
税制非適格ストックオプションの株式を保有する時の税率は、最大で55%程度となります。
③信託型ストックオプション
「信託型ストックオプション」は、通常のストックオプションとは異なり、従業員に直接権利が与えられません。
会社が成長する前に発行していたストックオプションを発行、信託しておき、信託契約の受託者から間接的に権利を与えられるもののことをいいます。
④有償型ストックオプション
「有償型ストックオプション」とは、株式売却時にのみ税金が発生するストックオプションです。通常のストックオプションは、株式保有時および株式売却時に税金が発生します。
なお、有償型ストックオプションは、株式を購入する際に有償となるので、注意が必要です。
⑤株式報酬型ストックオプション
「株式報酬型ストックオプション」は、権利行使価格を低く設定し(通常1円)、株式自体が報酬となるストックオプションになります。
主に、退職金として利用されることが多いストックオプションです。
2、ストックオプション導入の手続き

ストックオプションを導入しようか悩んでいる経営者の方は、多いのではないでしょうか。
今回は、ストックオプションを導入するためにどんな手続きが必要なのか、簡単な流れを紹介します。
流れは、以下のようになります。
- (1)募集事項の決定・通知
- (2)割当契約の締結・発行
- (3)新株予約権原簿の作成・登記
(1)募集事項の決定・通知
ストックオプションを導入するためには、募集事項を取締役会や株主総会等で決定する必要があります。
主に決めなければいけない募集事項は、以下の通りです。
- 新株予約権の内容と数量
- 割当日
- 振り込み期日
募集事項が決定したら、割当日の2週間前までに、株主に通知する必要があります。
(2)割当契約の締結・発行
次に、発行者である会社と付与対象者の間で、新たに発行する新株予約権を引き受ける割当契約を締結します。
ストックオプションは、一般的に「総数引受方式」という手続き方法がとられます。
「総数引受方式」とは、通常の新株予約権発行の際に必要である会社からの通知等が不要である手続き方法をいいます。
ストックオプションでは、付与対象者と割当数が決定していることが一般的です。
ストックオプションの付与対象者は、割当契約の締結後、割当日に新株予約者となります。
(3)新株予約権の原簿作成・登記
最後に、新株予約権を発行した会社は、発行後速やかに、新株予約権原簿を作成しましょう。
新株予約権原簿には、以下の情報を記載しなければなりません。
- 新株予約権取得者の氏名や住所
- 新株予約権の内容
- 証券番号
新株予約権原簿の作成と同時に、新株予約権の登記は割当日から2週間以内に行う必要があります。
登記に記載する主な事項としては、以下の通りです。
- 新株予約権の数
- 新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法
- 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
- 金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
- 新株予約権の行使期間
- 上記以外に新株予約権の行使の条件を定めた場合はその条件
以上の3段階が、ストックオプション導入までの簡単な流れとなります。
3、ストックオプションのメリット・デメリット
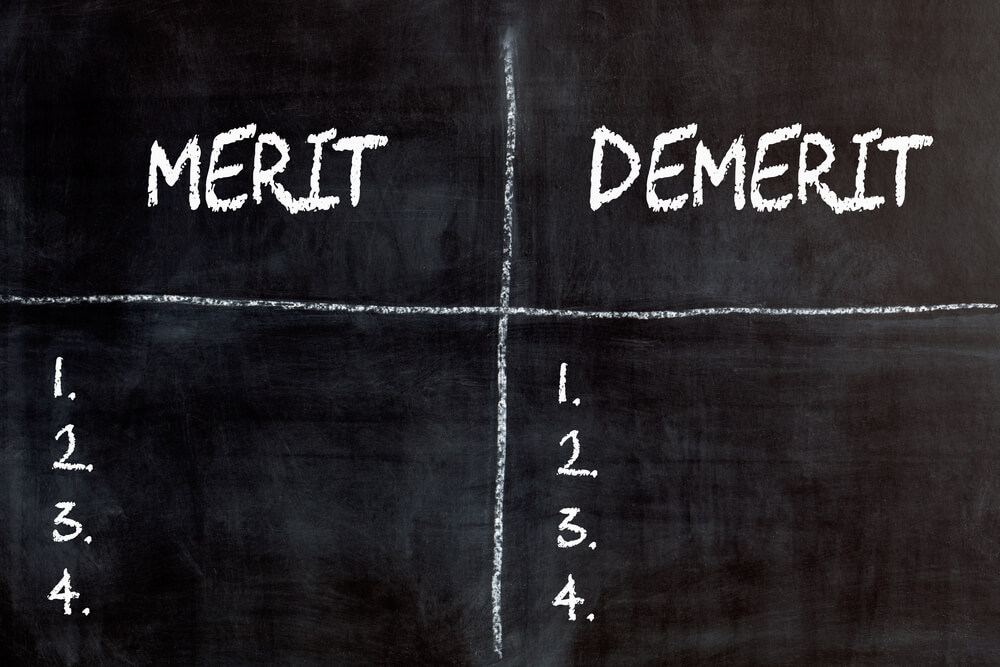
ストックオプションは、従業員のインセンティブを高める制度のひとつですが、ストックオプションを発行する会社にとってもメリットはあるのでしょうか。
本章では、ストックオプションのメリットとデメリットについて詳しく紹介します。
(1)メリット
ストックオプションは、権利を与える会社と従業員の両方にとってもメリットが高い制度といえます。
ストックオプションの主なメリットは、以下のとおりです。
- 優秀な人材の確保
- 従業員の活力になる
- 通常の株式よりもリスクが少ない
①優秀な人材の確保
ストックオプションは、従業員にとって魅力が高い人気のインセンティブ制度です。
ストックオプションがあることで、将来的な株価上昇を期待して優秀な人材を確保することができます。
②従業員の活力になる
ストックオプションは、自分が働く会社の株式を取得する権利です。
自社の株式の市場価値が高くなるほど、報酬を多く受け取ることができます。
会社への貢献が、自分の利益に反映する可能性があるため、従業員のモチベーションは高まるでしょう。
③通常の株式よりもリスクが少ない
安い価額で自社株式を取得できるストックオプションであれば、通常の株式のように売却価額が購入価額を下回る可能性が低くなります。
(2)デメリット
対して、ストックオプションには、デメリットも存在します。
デメリットを考慮した上で、導入するかどうか決定しましょう。
紹介するデメリットは、以下のとおりです。
- 株価低下のリスク
- キャピタルゲイン後の活力低下や流出
①株価低下のリスク
自社の経営が好調でも、国の経済状況が悪かったり、関連会社の不祥事だったり、自社の努力以外の要因で株価が下落することがあります。
株価が下落し続けると、「自社の株価が上がらないんだったらやる気が出ない……」という従業員が増える可能性も考えられます。
最悪の場合、株価下落によって自社の成長を見込めなくなった従業員が、他社へ流出してしまうかもしれません。
②キャピタルゲイン後の流出や活力低下
ストックオプションの利益を大きくするために、自社の株式上昇させようと貢献したけれど、利益を得た後はやる気が出ないという従業員が出てくる可能性があります。
ストックオプションに魅力を持って入った優秀な人材も、キャピタルゲインを得たらすぐに会社を辞めてしまうということもあるかもしれません。
4、ストックオプション導入のポイント

ストックオプションの導入を決めたら、導入する際のポイントについて知っておきたいのではないでしょうか。
今回紹介するストックオプション導入のポイントは、以下のとおりです。
- ストックオプションに向いている会社
- ストックオプションの持分比率
(1)ストックオプションに向いてる会社
ストックオプションに向いている企業は、以下のとおりです。
- 採用にお金を掛けられない
- 優秀な人材を採用したい
- 株式上場を目指している企業
特に、株式上場を目指している会社は、将来的に業績が大きく伸びる可能性を秘めています。
ストックオプションは、発行時の価値よりも売却時の価値が大きければ大きいほど、報酬が高くなります。
株式上場を目指している会社にとっては、優秀な人材が必要になり、ストックオプション制度を採用すれば、採用にお金を掛けなくても優秀な人材を確保することができるでしょう。
(2)持分比率
ストックオプションは、発行しすぎてはいけません。
発行しすぎてしまうと、既存の株主が保有している株式の価値が低下します。
株式の価値低下に伴って、投資家が株式を売却することになったら株価が急激に下落するかもしれません。
会社の株式におけるストックオプションの持分比率は、「10%」程度が望ましいとされています。
5、ストックオプション導入でプラスになるか検討しよう

ストックオプションを導入すれば、誰でも利益が生まれると期待されがちですが、株価の下落によって報酬の価値が下がることもあります。
ストックオプションを導入する際には、プラスになるのかどうか必ず検討しましょう。
(1)検討方法
ストックオプション導入を検討している経営者の中には、「ストックオプションの知識が乏しく、相談できる人もいない……」という方も少なくないのではないでしょうか。
上記のような経営者の方に向けて、ストックオプション導入に関して、「税理士に相談する」という方法を紹介します。
税理士に相談すれば、どれぐらい効果があるか、他社の事例などを紹介してもらうことができます。
ストックオプションに関して多くの事例を見ている税理士と共に、ストックオプションを導入するかどうか決定すれば、安心感が生まれるでしょう。
税理士へ依頼するメリットの詳細については、次項で紹介します。
(2)税理士に依頼するメリット
ストックオプションに関して、税理士へ依頼する具体的なメリットは、以下のとおりです。
- ストックオプションについて詳しく説明
- 他社の事例を紹介
- ストックオプションの効果がどれくらいになるか説明
- 自社の経営状況を踏まえて、導入するかを判断
- 募集事項の決定の手助け
- 原簿の作成
- 税制関連についての手厚いサポート
上記のように、税理士に依頼すると、設計などの導入から実務までサポートしてもらうことに加えて、導入後も、手厚いサポートを受けることができます。
ストックオプションは、税金が発生するインセンティブ制度です。
「税金がいくら発生するのか」「確定申告の手続きはどうすればよいか」など、煩雑な点も多くなっています。
税務のプロである税理士に相談すれば、的確なアドバイスを期待できるでしょう。
まとめ
今回は、資金調達方法の1つ「ストックオプション」について解説しました。
ストックオプション導入の参考になりましたでしょうか。
ストックオプションは、自社株式を安く購入できるという制度です。
従業員にとって魅力的なインセンティブ制度であり、近年導入する企業が増えています。
導入するにあたっては、税理士に相談・依頼することがおすすめです。
税理士に相談すれば、導入前から導入の手続き、その後の手厚いサポートまで受けることができます。
ストックオプションの導入を検討しているものの、不安がある方はぜひ一度、税理士へ相談してみてはいかがでしょうか。
税理士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
初回のご相談は無料ですので
お気軽にべリーベスト税理士事務所までお問い合わせください。
最近の投稿

贈与税と相続税対策としての生前贈与について

ChatGPTと専門家サービス活用について

電子帳簿保存法とは?ポイントと猶予について

【中小企業向け】経営者・役員退職金の準備方法について

フリーランス(個人事業主)の最適な資産形成とは?小規模企業共済、iDeCo、つみたてNISAを徹底比較!

資産形成を成功させるポイントとは

円安が資産運用に与える影響は?円安時の投資のポイントも解説

事業再構築補助金とは?サービス産業を救う補助金の6つのポイント

マイナンバーの管理とシステム導入を企業で行うためのポイントを解説