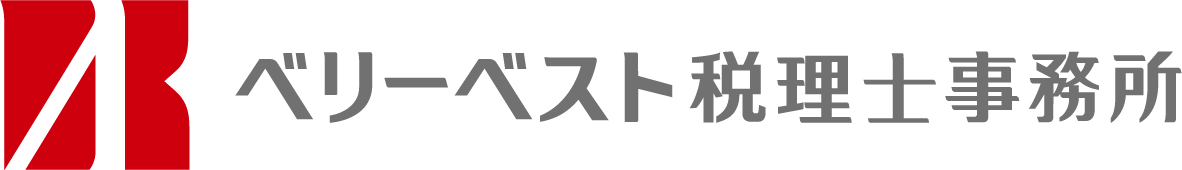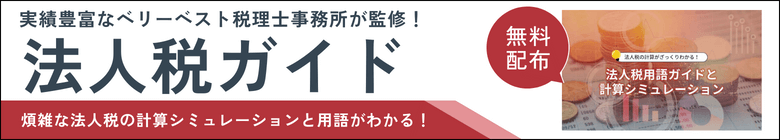銀行融資を高額・低金利・早く受けるための7つのポイント

銀行融資を高額かつ低金利、さらに早めに受けたい!
資金調達で銀行融資を受けようと考えている経営者の方にとって、低金利で高額な融資を早めに受けられるのは、非常に魅力的ですよね。
ところが、銀行融資の金利は思ったより高いイメージ……。審査に時間がかかってしまうということも。
高額な銀行融資を低金利で時間をかけずに受ける方法は、存在するのでしょうか。
今回は、銀行融資の基本事項を説明したうえで、
- 低金利の銀行融資は存在するのか
- 低金利で高額な融資を受ける方法
- どれくらい銀行融資を受けるべきか
- 銀行融資を受けるためにやってはいけないこと
など、銀行融資に関することについて解説します。
他にも、銀行融資以外の資金調達方法や、銀行融資について相談できる税理士の探し方についても紹介します。
この記事を参考に、低金利で高額の銀行融資を受けるためのポイントをおさえましょう。
税理士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
お気軽にべリーベスト税理士事務所までお問い合わせください。
1、銀行融資とは

「銀行融資」は、銀行からお金を借りることです。返済義務があり、「デット・ファイナンス」ともいいます。
まずは、銀行融資の目的とメリットについて確認しましょう。
(1)銀行融資の目的
「銀行融資は、つまり借金では?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、一般的な「借金」のイメージとは異なります。
借金は、生活費や娯楽などの消費を目的とした行為です。
銀行融資は、事業のために使うという目的があります。
なお、銀行融資を受けるためには、審査に通過しなければなりません。単に融資の申請をしただけでは、審査を通過することは難しいでしょう。
(2)銀行融資のメリット
銀行融資を利用するメリットは、次の4つが考えられます。
①資金調達しやすい
銀行融資の一番のメリットは、資金調達しやすいという点です。
具体的には、審査さえ通過してしまえば一度に高額な融資も可能になります。
銀行融資には返済義務があり、元金を返済するのに加えて、利息を支払わなければなりません。
保証協会を付ければ、万が一業績が悪くなり返済できなくなっても、一定限度までの保証がつきます。融資先視点でみても、貸倒リスクが小さい投資方法といえるでしょう。
銀行融資は、返済期日までに遅滞なく返済することで、企業の返済実績を作ることができます。
返済実績を作ることによって、次に資金調達をする場合にも融資の審査が通りやすくなったり、さらに好条件で融資を受けたりできるでしょう。
なお、はじめて銀行融資を受ける場合には、2回目以降の銀行融資よりも審査通過の難易度が高くなります。
会社を大きくしていくためには、最初の銀行の審査をどのようにクリアするかが重要なポイントです。
②節税対策になる
銀行融資は、節税対策にもなります。
「借入をしているということは、損をしているのでは?」とお考えの方もいるでしょう。
銀行融資には、元本と利息についての返済義務があるため、金銭的には損をしているといえます。
しかし、税務において支払った利息分は「費用/損金」となり、利益所得から支払った利息分を差し引くことができるので、節税効果があるのです。
③経営権に影響がない
例えば、株式による資金調達の場合、保有株式数が多い株主の議決権が大きくなります。
結果として、経営権が経営者以外にわたってしまい実際に出資者から経営に口出しされる可能性があります。
人によっては、「株を売ることは体の一部を売ること」と考える方もいます。
他人が自社の株式を保有していることで、経営者の思う経営ができず、不自由になってしまう可能性があるのです。
一方、銀行融資による資金調達では、経営権が第三者に影響されません。
金融機関や投資家の承認を得る必要がなく、経営者の自由なように経営を続けられるのです。
④返済金額が決まっている
銀行融資では、元金と利息分の決まった金額を銀行へ返済します。
株式のように、配当金を支払ったり優待を贈呈したりする必要はありません。
銀行融資はあらかじめ返済金額が決まっているため、資本コストが株式と比較すると抑えられ、資金計画を立てやすくなります。
(3)コロナ禍でもそれ以外でも倒産しないためには「キャッシュ」を持とう
2020年、新型コロナウイルス感染拡大の影響によって、世界中で経済に大きな打撃を与えました。倒産してしまった企業も、例年より大幅に増えています。
コロナの収束が立たないなか、会社を倒産させないためには、キャッシュを保有し続けることが重要なのです。
借入というかたちですが、銀行融資ではキャッシュ(現金)を調達できます。
会社経営を持ち直すために、まずは融資を検討しましょう。
2、低金利の銀行融資は存在する?

低金利の銀行融資は、存在するのでしょうか。
銀行融資の金利がどのように決まるかについて説明したうえで、低金利の融資を紹介します。
(1)銀行融資の金利はどのように決まるか
銀行融資の金利は、融資の種類や融資先の企業によって幅があります。
すでに説明しているように、融資を受けるためには審査を通過しなければなりません。
審査によっても、金利は変動します。
例えば、企業の信用力が低いと、将来倒産の危険があるとみなされてしまうため、金利を高くされることがあります。
1回目の融資は金利3%であったのに、5回目の融資では金利1%というように、返済実績を作るうちに金利が低くなっていくこともあるでしょう。
また、返済期間も金利に影響します。
短期なら低金利で借りられるが、長期だと金利が高めになってしまうこともあるのです。
(2)日本政策金融公庫の融資は中小企業向け!
日本政策金融公庫は、中小企業を支援するために、政府が100%出資している機関です。
銀行などの金融機関が行う金融を補完することを目的として、中小企業向けに融資を提供しています。
日本政策金融公庫で提供している融資制度は、融資期間などによって変動しますが、低金利といえるでしょう。
例えば、中小企業事業に対する融資の場合、10年以内の融資なら金利は1.11%です(令和3年1月4日現在。「中小企業事業(主要利率一覧表)」―日本政策金融公庫参照)。
また、日本政策金融公庫が提供するすべての融資は、保証協会を経由しませんので、保証料も不要です。
それぞれの融資制度において融資条件に合致すれば、基本的にほとんどの中小企業が保証料なしで受けられます。
創立したての企業や初めて融資を受ける会社でも、日本政策金融公庫の融資は他の銀行融資に比べると受けやすいのが魅力でしょう。
3、低金利で高額な銀行融資を早く受けるための方法

銀行融資を利用するなら、金利はできるだけ低い方を選びたいですよね。
加えて、融資の審査も早めに対応してくれると助かるのではないでしょうか。
融資の種類や企業の信用力、返済期間などが影響するため、金利は企業によって異なることはすでに説明したとおりです。
それでも、低金利で高額な融資を受けるためには、次のような方法を実践してみましょう。
(1)決算書を整える
融資の審査に際してさまざまな書類を提出しますが、「決算書」も提出書類のなかの一つとなります。
融資の審査において、企業の信用に大きな影響を与えるのが、貸借対照表や損益計算書などの「決算書」です。
決算書をしっかりと整えることで、審査もスムーズに通過できるでしょう。
銀行が決算書の内容で重視するのは、次の5つです。
- ①事業の利益がある
- ②売上が伸びている
- ③債務超過がない
- ④役員への貸付などがない
- ⑤資金繰りができそう
- ⑥返済力がある
それぞれの点について、どのような部分が注目されるのか、より詳しくみていきましょう。
①事業の利益がある
銀行は、会社の事業によって利益が出ているかどうかによって、基本的な返済力をみています。
事業ではなく、株による利益などについては評価しないことが多いでしょう。
損益計算書では、特に「営業利益」や「経常利益」をチェックします。
「営業利益」は、売上から原価と経費を差し引いた利益です。
「経常利益」は、利息の支払いを含めた通常の企業活動による損益を示しています。
特に、経常利益が黒字であれば、銀行は企業を高く評価してくれる傾向があります。
銀行としては、「利息を支払ってもこの企業にはお金の余裕がある」と判断できるからです。
また、銀行は単年度の売上だけで審査をするわけではありません。
過去の利益の推移についても、チェックします。
経常利益が3年以上黒字であれば、銀行からの評価は高くなるでしょう。
現在黒字であっても過去に赤字があれば、銀行から「また赤字になってしまうのでは?」と評価される可能性があります。
一方、長らく黒字であったのに、現在赤字になってしまった場合も「これから赤字が続くのでは?」と評価が下がってしまいかねません。
以上の場合には、今後の事業計画をしっかり説明して、「黒字を継続する」もしくは「黒字へ巻き返す」という意思を主張できるとよいでしょう。
②売上が伸びている
売上が伸びている会社は、利益があり将来的にも成長性があるため、経営が安定するであろうと判断できます。
銀行は審査の際、決算書の損益計算書における「売上総利益」をチェックします。
売上総利益とは、売上から直接の原価を引いた利益のことです。
差し引くのは「直接の原価のみ」で、給料や地代、販促費などは差し引かれていません。
売上総利益が赤字の場合、銀行としては信用が低くなってしまいますので、注意が必要です。
また、売上が伸びると売掛金や棚卸資産も増えます。
売掛金や棚卸資産が、売上に比べて多すぎる場合には、注意が必要です。
銀行から架空計上を疑われる可能性があります。
売掛金や棚卸資産の割合が大きいならば、銀行からの信用を失わないためにも、しっかりと事情を説明できるようにしましょう。
③債務超過がない
銀行は、貸借対照表のうち「純資産」の項目がプラスになっているかどうかをチェックします。
純資産がマイナスになっていると、債務超過で負債が資産を上回っていることになり、印象がよいものではないでしょう。
原則、銀行は債務超過がある会社に対して融資を行いません。
具体的には、増資の検討や負債項目のチェックをするとよいでしょう。
④役員への貸付がない
役員貸付金は、会社が役員に貸しているお金のことです。
貸借対照表では「貸付金」の勘定科目になります。
貸借対照表で役員貸付金が残っていると、「融資をしたら役員がそのお金を使ってしまうのでは?」と金融機関の心証が悪くなってしまいかねません。
結果として、融資の審査において役員貸付金は「役員の私的利用のため」と判断されます。
融資を受ける場合には、役員貸付金を解消しておきましょう。
⑤資金繰りができそう
銀行は、融資をしたら資金繰りができるかどうかを確認します。
融資の新生児に資金繰り表を提出して説明することが多いですが、資金繰りができなさそうな計画だと、融資は見送られるでしょう。
⑥返済力がある
①で説明したような、基本的な返済力の他にも、返済力として次のような点をチェックされます。
- 他の金融機関から融資を受けているか
- 資金調達の余力があるか
- 経営者の個人資産
(2)返済期間を短期間にする
銀行から融資を受ける場合、返済期間によって金利が変動します。
例えば、3年以内の融資の場合には金利が2.6%、5年以内なら2.9%、10年以内なら3.5%……というように、返済期間が長くなれば長くなるほど金利も高くなる傾向にあります。
低金利で融資を受けるなら、短期間で返済するようにしましょう。
ただし、短期で返済するとなると、毎月の返済額が大きくなるのでキャッシュフローを圧迫してしまいます。
金利を重視すべきか、返済期間を重視すべきかのバランスを見極めることが重要です。
(3)信頼される経営者になる
融資に限った話ではありませんが、周りから信頼される経営者になることで、金融機関からのイメージがよくなります。
実際、銀行の融資担当者のなかには「経営者を見て融資するか判断する」という方も少なくありません。
今までの返済実績や決算書の内容だけでなく、経営者の事業に対する姿勢や考え方なども、融資の審査には重要な資料となるのです。
銀行からの信用力を高めれば、審査の期間も早く、低金利で高額な融資を受けることができるでしょう。
4、どれくらい銀行融資を受けるべき?

低金利で高額な融資を受けたいといっても、いったいどれくらいの金額で融資を受ければよいのでしょうか。
融資額については、「自己資本比率」が重要です。
本項では、適切に銀行融資を受けるために意識したい自己資本比率のポイントを解説します。
(1)自己資本比率のバランスを見極める
自己資本比率とは、貸借対照表の総資産に占める「自己資本(純資産)」の割合です。
つまり、「貸借対照表から会社の安定性を判断できる指標」です。
自己資本比率は、次の計算式で求められます。
- 自己資本比率=自己資本÷総資産
上記の計算式は、次のように展開できます。
- 自己資本比率=自己資本÷(他人資本+自己資本)
自己資本比率が低ければ、借入金や未払金などの負債が多いということです。
一方、自己資本比率が高ければ、返済義務のないお金が十分に会社にあるといえます。
客観的にみると、自己資本比率が高い企業は中長期的に倒産しないと判断されるのです。
企業にとって、資金調達の方法として融資は必要不可欠となります。
しかし、すでに説明したように、銀行融資は借入です。貸借対照表において、「負債」扱いになってしまいます。
会社経営のためには、一定以上の基準で自己資本比率を保ちつつ、負債と純資産のバランスから金額を見極めながら銀行融資を利用しましょう。
(2)自己資本比率を高めるには
時間やコストをかけずに、自己資本比率を高めたい……という経営者の方も多いのではないでしょうか。
さきほどの自己資本比率の計算式にもとづくと、自己資本比率を向上させる方法は次の2つです。
- 他人資本(負債)を減らす
- 自己資本(純資産)の額を増加させる
自己資本比率を高めるためには、具体的に次で紹介することを実践してみましょう。
①繰越利益余剰金を増加させる
会社に利益が出たとき、むやみな資金投下を行わず社内留保することで、繰越利益剰余金を増やし、自己資本比率を高めることが可能です。
繰越利益剰余金は、過去の税引後純利益の蓄積です。会社の経営安定性を左右する重要な要素といえるでしょう。
業績が良く利益をより多く出せる会社であれば、自然と利益の社内留保である利益剰余金は増え続け、会社の成長とともに自己資本比率を高められます。
②増資を行い資本金を増加させる
自己資本比率を高めるもう一つの方法は、資本金を増加させることです。
株式発行によって増資を行い資本金を増やすと、自己資本を増やすことができます。
以上のように、繰越利益余剰金の増加または増資によって、自己資本比率が増加します。
特に、繰越利益余剰金が順調に増加しているということは、銀行にとっての安心材料になるため重要です。
(3)一方で「借りられるだけ借りる」という考えもある
「自己資本比率が低くても良いから借りられるだけ借りる」という考え方もあります。
そもそも、中小企業が倒産するのはどのようなケースでしょうか。
赤字の場合、必ず倒産するのでしょうか。
いいえ、企業は赤字でも倒産しません。
「現金がゼロになったら」倒産するのです。
すでに説明しましたが、コロナ禍などで業績が悪化しても現金をなくさないためには、銀行からきちんと資金調達して、十分なキャッシュを持っておくことが重要です。
以上のことから、「倒産しないために借りられるだけ借りておく」というのも、重要な選択肢といえるでしょう。
しかし、銀行は「返済してくれる」と確信できないと、なかなか貸してくれません。
無尽蔵に銀行融資を受けることは、基本的に不可能なのです。
結果として、自己資本比率は下がってしまいますが、「倒産しない」方が経営においては重要性が高いでしょう。
自己資本比率の維持を重視して調達するか、それとも借りられるだけ借りるかのいずれが経営判断として適切かは、会社の成長フェーズにより異なります。
もし判断に困るようであれば、ビジネスや財務に詳しい税理士に相談するとよいでしょう。
5、要注意!銀行融資を受ける際にやってはいけないこと

(1)無計画で融資を申し込む
融資を申し込む場合、何のためにどれくらいの金額を融資してもらいたいのかを明確にせず無計画のままでは、銀行も融資をしてくれません。
銀行から必要書類の提出を求められているにもかかわらずすぐ提出できないという場合も、「無計画」という印象を与えてしまうでしょう。
「無計画」と判断されないためには、社内のお金の支出や売上の推移などを把握することが重要です。
予めきちんと事業計画(売上・利益の数値計画、人員計画等)を立て、月次決算を行うようにします。
具体的には、次のような点を意識するとよいでしょう。
①経営者自身が決算書や試算表の内容を説明できるようにする
経営者自身が会社の経理に無関心では、決算書や試算表が不明確となってしまうでしょう。
融資を受ける際には、銀行へしっかりと会社のお金の状況を提示しなければなりません。
経営者自身が、決算書や試算表の内容を説明できるようになることが大切です。
②経理担当者が経理業務を理解する
小規模な企業では、人材不足などで一人が事務と経理業務を担っている……というケースも少なくないでしょう。
業務量が多く、そもそも経理担当者が経理業務を把握しきれていないというようなこともあるかもしれません。
①でも説明したように、経営者が会社のお金の状況を把握できるためには、経理担当者とのコミュニケーションが大切です。
(2)会社の成長性や将来性を明確にしない
経営戦略を立てず、行き当たりばったりの経営をしている場合、安定的な経営は見込めません。
業績が悪くなれば融資を繰り返すことになり、最終的には経営破綻となってしまうでしょう。
長期的な目標がなく、目先のことしか見えていない会社に対して、銀行は融資をしたいと思いません。
他にも、経営者が高齢であるにもかかわらず、後継者が決まっていないというような場合も同様です。
高齢の現経営者に万が一のことがあった場合、融資を返済できるのかという点が懸念されるからです。
将来的に、会社をしっかり支えていける後継者へ会社経営を任せるということも、銀行融資を受けるためには重要なポイントとなります。
6、銀行融資以外の資金調達方法

銀行融資の他にも、資金調達方法には選択肢があります。
今回は、次の資金調達方法を紹介します。
- 株式発行
- 社債発行
- 資産売却
それぞれの特徴や、メリットなどを説明します。
(1)株式発行
株式発行は、名前のとおり新株を発行して資金を調達する方法です。エクイティ・ファイナンスとも呼ばれます。
株式発行によって得た資金は、貸借対照表の「資本」に記載されます。
この点で、融資とは異なり返済する必要がない資金調達方法です。
保有株式数の多い株主に議決権が傾いてしまい、会社の経営権自体を経営者以外が握る可能性があるため注意しましょう。
(2)社債発行
企業が社債を発行し、資金調達を行う方法もデット・ファイナンスの一つです。
社債は「企業の借金証書」で、発行した企業にとっては借金となります。
「いくら借りたか、どれくらい利息があるか、返済期限いつか」という事項が記載されています。
融資とは異なり、企業が直接資本市場で資金調達をする方法です。
また、50人未満の投資家へ発行する「私募債」という社債もあります。
私募債は、スタートアップのベンチャー企業や、実績があまりない中小企業などでも比較的行いやすいでしょう。
(3)資産売却
資産の信用力を用いて融資を受け、資金を調達するのが資産売却です。アセット・ファイナンスとも呼ばれます。
不動産を担保とした融資の他に、動産や債権、知的財産権など資産でもキャッシュフローを生むものであれば、資産売却の対象となります。
7、適切な銀行融資を受けるために税理士へ相談するのがオススメな理由

(1)ビジネスや自社の業界について理解がある
税理士のなかには、ビジネスの原理原則に詳しい税理士も存在します。
ビジネスに詳しい税理士なら、会社の税務に関することだけではなく、業績向上のためのアドバイスをしてくれるでしょう。
具体的には、適切に銀行融資を受けるために会社の財務状況をもとに、将来的にどのような資金調達を計画すればよいかのアドバイスなどを期待できます。
また、自社の業界の知識を持っている税理士なら、財政状況から今後どのように経営を進めればよいかなど、より具体的なアドバイスを期待できるでしょう。
ビジネスやあなたの会社の業界について詳しい税理士は、銀行融資を受ける際に強力な味方となってくれるはずです。
(2)経理業務をフォローしてくれる
税理士は、会社の経理業務を一括してフォローしてくれます。
毎月、税理士に月次決算を行い監査してもらうことで、社内の業績を随時確認することが可能です。
月次決算は非常に手間のかかる作業ですが、税理士に依頼すれば負担が大幅に減るでしょう。将来的な経営戦略を立てるために、税理士は必須な存在です。
結果として、税理士に依頼することは、あなたの会社の業績アップに繋がるでしょう。
なお、月次決算などの業務を税理士に依頼するなら、対応が早くて丁寧に作業してくれる税理士を選びましょう。
まとめ
今回は、「高額かつ低金利で銀行融資を受けるために知りたいこと」を中心に解説しました。
銀行融資には返済義務がありますが、返済額があらかじめ決まっています。
他の資金調達方法に比べて取り入れやすく節税対策にもなり、経営権に影響を与えない資金調達方法です。
銀行融資によって資金調達する場合は、自己資本比率を高めることが特に重要です。
今回説明した融資に関するポイントを参考に、銀行融資をうまく利用して資金調達を行いましょう。
税理士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
初回のご相談は無料ですので
お気軽にべリーベスト税理士事務所までお問い合わせください。
最近の投稿

贈与税と相続税対策としての生前贈与について

ChatGPTと専門家サービス活用について

電子帳簿保存法とは?ポイントと猶予について

【中小企業向け】経営者・役員退職金の準備方法について

フリーランス(個人事業主)の最適な資産形成とは?小規模企業共済、iDeCo、つみたてNISAを徹底比較!

資産形成を成功させるポイントとは

円安が資産運用に与える影響は?円安時の投資のポイントも解説

事業再構築補助金とは?サービス産業を救う補助金の6つのポイント

マイナンバーの管理とシステム導入を企業で行うためのポイントを解説