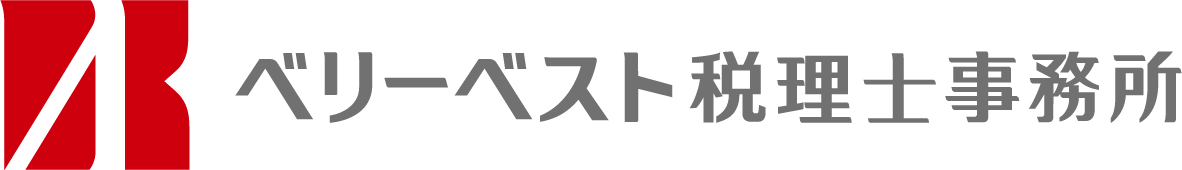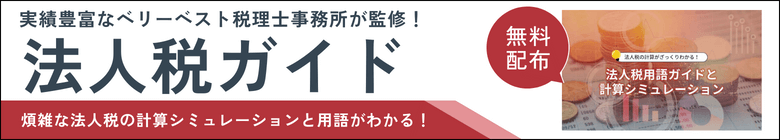税務調査に向けて知りたい!寄附金の3つのポイントと準備・対策

法人が支出する寄附金は、一定の金額を損金算入できます。
そのため、節税手段として活用されていますが、
「税務上の取り扱いがよくわからない。」
「税務調査が来たら、どう備えればいいんだろう?」
という声をよく耳にします。
実際、寄附金の処理はあいまいになりやすく、税務調査では狙われやすい項目です。
今回は、「否認されて追加で税金を納付したくない。」というお悩みを持つ経営者の皆さまに向け、
- 税務上の寄附金の概要
- 寄附金の損金算入限度額
- 税務調査でのポイント、準備・対策
を解説していきます。
この記事を読めば、寄附金の基本的な税務上の取り扱いと税務調査に向けた準備・対策を知ることができます。
その結果として、税務調査が来るかもしれないという精神的負担を軽減させることができるでしょう。ぜひ、最後までご覧ください。
本記事は、べリーベスト税理士事務所の公式YouTubeチャンネルで公開されている以下の動画と連動しておりますので、ぜひ併せてご覧ください。
税理士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
お気軽にべリーベスト税理士事務所までお問い合わせください。
1、税務調査における寄附金の注意点について知る前に~寄附金とは

(1)税務上の寄附金
「寄附金」には色々な種類があります。
まず思い浮かぶのは、「赤い羽根の募金」や「災害義援金」、「神社などへの喜捨金」ではないでしょうか。
イメージとしての寄附金は、前述のとおりです。
税務上の寄附金は、以下のように定義されます。
| 事業と関係の薄い者に対して、金銭や資産などを無償で譲渡・贈与した場合における、 支出した金銭の額や資産の価額。 |
(参考:法人税法第37条第7項)
上記の定義における「無償」とは、「見返りを求めない(反対給付を伴わない)」という意味です。
税務上の寄附金の範囲には、以下のものも含まれます。
- 名目が「拠出金」や「見舞金」であるが、実質的には寄附と見なされるもの
- 資産などを低額で譲渡した場合の時価との差額
交際費等や広告宣伝費、福利厚生費などに該当する支出は、寄附金には含まれません。
「会計上の寄附金」は費用となりますが、税務上は損金算入限度額が設けられています。無制限に損金となるわけではないため注意が必要です。
(2)寄附金の区分
寄附金は支出の対象によって区分が分けられています。
①一般の寄附金
②~⑤以外の寄附金は一般の寄附金といい、以下のような支出が該当します。
―一般寄附金の例
- 神社などへの支出(祈祷料など)
- 政治団体への支出
- 町内会への支出
- 資産などの低額譲渡
②国等に対する寄附金と指定寄附金
国や地方公共団体への寄附のほか、財務大臣が指定する緊急性や公益性の高いと判断された寄附金(指定寄附金)が該当します。
―国等に対する寄附金、指定寄附金の例
- 国や地方公共団体に対する支出
- 共同募金(赤い羽根の募金など)に対する支出
- 被災した地方公共団体に対する支出(義援金)
③特定公益増進法人に対する寄附金
特定公益増進法人とは、教育や科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献などに寄与する法人をいいます。
特定公益増進法人の主業務に関連する寄附金を支出した場合は、一般の寄附金とは別枠で損金算入できます。
―特定公益増進法人の例
- 独立行政法人
- 日本赤十字社
- 社会福祉法人
- 更生保護法人 など
(参考:特定公益増進法人に対する寄附金)
④特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
公益信託とは、学術や技芸、慈善、祭祀など公益目的のために、個人や法人が金銭などを銀行に信託することをいいます。
公益信託のうち、一定の要件を満たしたものが特定公益信託です。
(参考:寄附金を支出したとき)
⑤認定NPO法人等に対する寄附金
特定非営利活動法人(NPO法人)のうち、一定の基準を満たし、都道府県知事や指定都市の長などから認定を受けた法人を「認定NPO法人」といいます。
認定NPO法人は、法人自身と寄附者に税制上のメリットがあります。
(参考:認定NPO法人等に対する寄附金、内閣府NPOホームページ)
(3)企業版ふるさと納税とは
企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)とは、法人が自治体に寄附をすると、税制上の優遇措置を受けることができる制度です。
地方自治体が実施する、「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に関連する支出をした場合に適用できます。
寄附額の約3割が損金算入できるほか、法人税、法人住民税、法人事業税から寄附額の約6割が税額控除が可能です。
よって、税金の軽減効果は最大で約9割となります。
適用期限は2025年3月31日までです。
(参考:企業版ふるさと納税ポータルサイト)
2、寄附金の損金算入限度額

法人が寄附をした場合、資本金や所得の金額、寄附金の区分により損金算入限度額が異なります。
(1)一般の寄附金
一般の寄附金の損金算入限度額は、以下の計算式で計算します。
―損金算入限度額の計算式
(資本金等の額× × × +所得の金額× +所得の金額× )× )× |
※x=当期の月数
―損金算入限度額の計算例
| 【前提】 ・資本金等の額:2,000万円 ・所得金額:3,000万円 ・当期の月数:12ヶ月 |
| 損金算入限度額 =(2,000万円×  × × +3,000万円× +3,000万円× )× )× =20万円 |
(2)国等に対する寄附金と指定寄附金
国や地方公共団体に対する寄附金や指定寄附金は、支払った全額が損金算入されます。
(3)特定公益増進法人に対する寄附金等
以下の①・②の、いずれか少ない金額が損金に算入されます。
- ①特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
②特別損金算入限度額
―特別損金算入限度額の計算式
(資本金等の額× × × +所得の金額× +所得の金額× )× )× |
※x=当期の月数
―特別損金算入限度額の計算例
| 【前提】 ・資本金等の額:2,000万円 ・所得金額:3,000万円 ・当期の月数:12ヶ月 |
| 特別損金算入限度額 =(2,000万円×  × × +3,000万円× +3,000万円× )× )× =97.5万円 |
上記計算例から分かるように、特定公益増進法人に対する寄附金は一般の寄附金と比較して、損金にできる金額が多く、優遇されているのが特徴です。
特別損金算入限度額を超えた部分の寄附金額は、一般の寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入されます。
なお、「特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭」と「認定NPO法人等に対する寄附金」は、特定公益増進法人の寄附金に含めて損金算入額を計算します。
以下の表に、主な寄附金の区分と損金算入限度額をまとめました。
区分ごとの計算方法を間違えないために、ある程度は覚えておいた方がよいでしょう。
| 区分 | 損金算入限度額 |
| 一般の寄附金 | 「2、(1)」の計算式による |
| 国等に対する寄附金と指定寄附金 | 支出の全額を損金算入 |
| 特定公益増進法人に対する寄附金 | 寄附金の合計額と特別損金算入限度額(「2、(3)」)の いずれか少ない金額(一般寄附金とは別枠) |
| 特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭 | 特定公益増進法人に対する寄附金に含める |
| 認定NPO法人等に対する寄附金 | 同上 |
(参考:寄附金を支出したとき)
3、寄附金について税務調査で注意したい3つのポイント

本章では、以下の2つについて詳しく解説します。
- 税務調査で寄附金の項目がよく見られる理由
- 税務調査で注意したい寄附金に関する3つのポイント
(1)寄附金が税務調査においてよく見られる理由
寄附金は税務調査で重点的にチェックされます。
交際費等と同様に明確な判定基準がないことから、誤って処理する可能性が高いためです。
また、支出の一部を損金として認めるという性質上、区分を誤ると追加で税金を納付する必要があります。
(2)税務調査でよく見られる3つのポイントと準備・対策
税務調査でよく見られる3つのポイントは次のとおりです。
- 寄附金となるものが他の勘定科目で処理されていないか
- 社長個人が負担すべき寄附金ではないかどうか
- 寄附金の区分についてしっかり要件を満たしているかどうか
①寄附金となるものが他の勘定科目で処理されていないか
「1、寄附金とは(1)税務上の寄附金」で説明したとおり、名目が「拠出金」や「見舞金」であっても実質的に寄附であれば、寄附金として取り扱う必要があります。
さらに、交際費等と寄附金は混同しやすいです。
金銭や資産を譲渡・贈与した際は、交際費等と寄附金のどちらに該当するかを、慎重に判断しましょう。
②社長個人が負担すべき寄附金ではないかどうか
社長が個人的に負担するべき寄附金を法人名義で支出した場合、寄附金として認められないことがあります。
社長個人への役員報酬としてみなされ、個人の所得税を追加で納める必要も出てきます。
学校などへの支出は寄附金となりますが、例えば、社長の子どもが通っている大学に法人名義で寄附をしていた場合、個人的な寄附金と判断される可能性が高いです。
寄附の経緯や社長との関係性をよく確認し、支出の内容が個人的な寄附金に該当するかどうかを判断してください。
③寄附金の区分についてしっかり要件を満たしているかどうか
寄附金は「2、寄附金の損金算入限度額」で解説したように、区分により損金算入限度額が異なります。
一般の寄附金を別の区分と勘違いして処理してしまうと、加算金を支払う必要が出てくる可能性があります。
支出した寄附金が、どの区分に該当するかをよく確認しておきましょう。
4、寄附金についての税務調査に悩んだら税理士に相談

(1)判断の難しい寄附金についてのアドバイス
これまで説明したとおり、寄附金の税務調査でポイントになる点は以下の3点になります。
- 寄附金以外の勘定科目の中に、寄附金となるものがないか
- 個人的な支出ではないか
- 各区分の要件を満たしているか
上記のほか、資産などの低額譲渡や交際費等との混同も指摘事項として頻出します。
正しく確定申告を行うためにも、判断の難しい支出は、税理士からアドバイスをもらいましょう。
(2)税務調査に向けて必要な準備や対策に関するアドバイス
税務調査で否認されないためには、普段からの準備や対策が肝心です。
調査官に対し、適切な処理をしていることを証明するため、必要書類や寄附の経緯をしっかりと記録しておきます。
どのような資料を用意するべきかは法人によって異なりますので、あらかじめ税理士に相談しておくとよいでしょう。
まとめ
ひとことで寄附金といっても、一般の寄附金、指定寄附金、特定公益増進法人に対する寄附金など、細かく区分されています。
区分により損金算入限度額が異なるほか、個人的な寄附金として判定された支出は役員報酬として取り扱われるため、否認された場合は、法人・個人双方の負担が大きくなります。
普段から記録を残したり、寄附金と見なされる取引がないか確認したりして税務調査に備えましょう。
不安が残る場合は、税金のプロである税理士に相談することをおすすめします。
その他、税務調査に関する記事は以下をご参考ください。
税理士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
初回のご相談は無料ですので
お気軽にべリーベスト税理士事務所までお問い合わせください。
最近の投稿

贈与税と相続税対策としての生前贈与について

ChatGPTと専門家サービス活用について

電子帳簿保存法とは?ポイントと猶予について

【中小企業向け】経営者・役員退職金の準備方法について

フリーランス(個人事業主)の最適な資産形成とは?小規模企業共済、iDeCo、つみたてNISAを徹底比較!

資産形成を成功させるポイントとは

円安が資産運用に与える影響は?円安時の投資のポイントも解説

事業再構築補助金とは?サービス産業を救う補助金の6つのポイント

マイナンバーの管理とシステム導入を企業で行うためのポイントを解説